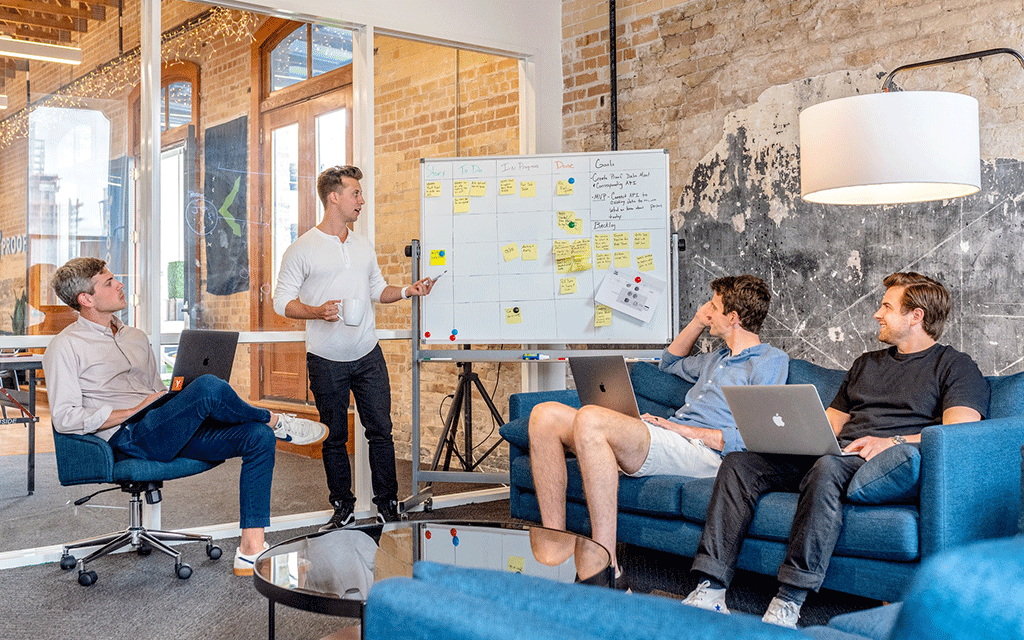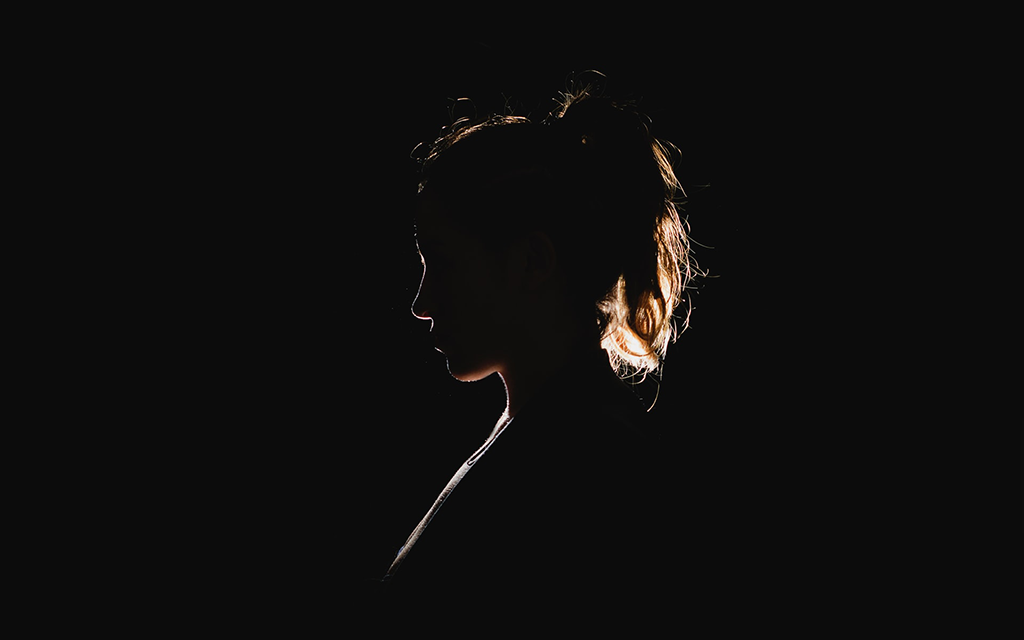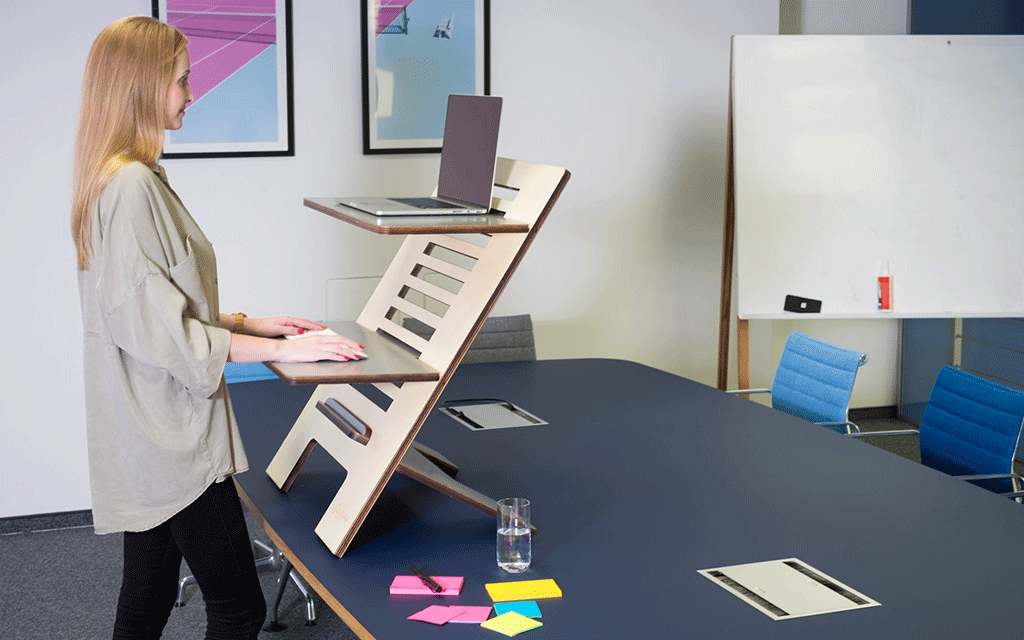こんな人におすすめ記事
- 簿記資格の勉強をしている
- 投資をしている
- 副業をしている
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 最近ネットショップのお手伝いをしてるんですけど、商品を仕入れたときの勘定科目って「商品」じゃないんですか?
 Yoshinori
Yoshinori 文記法で記帳するときは「商品」だけど、三分法で仕訳するときは「仕入」になるね。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 分記法?三分法?
 Yoshinori
Yoshinori 分記法と三分法は、商品売買取引のときに使用する仕訳で、簿記ではよく使用するから、ネットショップのお手伝いをするなら覚えておいた方がいいよ。
商品売買取引の仕訳方法
記帳の処理には、取引によってさまざまな方法があります。
その中でも企業活動における商品売買は事業の基本であり、処理をする発生件数も多くなります。
そのため日商簿記検定試験三級でも基礎的な知識として出題される傾向が高く、商品の売買に関することなのか、商品以外の売買なのかを抑えておく必要があります。
商品の売買に関する仕訳には、主に2種類があります。
- 分記法
- 三分法
今回はそれぞれの違いについて、解説していきます。
分記法は利益のわかりやすき記帳方法
分記法は、商品売買において「商品」という資産の勘定科目と商品売買益」という勘定科目を使って仕訳する記帳方法です。
その特徴は、仕入や売上の勘定科目を使用せず、仕入れた「商品」を手元に増えた「資産」として原価を借方に記帳し、販売したときはその商品の原価と、売価と原価の差額を「収益」として貸方に記帳します。
文記法で商品を仕入れたときの仕訳
例題
100円の商品を現金で仕入れた
(借)商品100(貸)現金100
文記法で商品を売買したときの仕訳
例題
100円で仕入れた商品を300円で売買した
(借)現金300(貸)商品100
(貸)商品売買益200
 Yoshinori
Yoshinori 文記法で仕入れた商品は「資産」として増加し、売買したときは「商品(資産)」の減少と「商品売買益(収益)」の発生をあわせて記帳するよ。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 分記法は、利益がいくらかすぐわかりますね。
三分法は最もポピュラーな記帳方法
三分法は、「仕入」「売上」「繰越商品」の3つの勘定科目を使った記帳処理の方法です。
簿記の商品売買の取引では、主に「三分法」を使用します。
なぜ「分記法」を覚える必要があるのかというと、三分法と分記法を比較することで、商品売買における勘定科目の「費用」と「資産」の違いを正しく理解しやすくするためです。
三分法で商品を仕入れたときの仕訳
例題
100円の商品を現金で仕入れた
(借)仕入100(貸)現金100
三分法で商品を売買したときの仕訳
例題
100円で仕入れた商品を300円で売買した
(借)現金300(貸)売上300
 Yoshinori
Yoshinori 三分法で仕入れた商品は、「仕入」として「費用」が発生し、「売上」として「収益」が発生したと考えるよ。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 分記法の方が書き方がシンプルですね。
三分法を使う理由
商品売買に関する基本的な仕訳の方法を見てきましたが、なぜ三分法を主に使うのか?
理由は簡単で、書き方がシンプルで簡単だからです。
ただし、分記法と違い三分法での書き方にはデメリットもあり、仕訳した内容を見ても利益がわかりません。
そのため、三分法を用いて仕訳した簿記は決算のときにまとめて儲けを計算します。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 企業の儲けがその都度わかった方がいいんじゃないんですか?
 Yoshinori
Yoshinori 商品売買は回数が多くなりがちだから、商品を販売するたびに文記法で書いちゃうと逆に煩雑になってわかりにくくなるんだよ。
まとめ
簿記の商品売買の基本「文記法と三分法の違い」について解説しました。
利益のわかりやすい分記法ですが、取引回数が多くなりがちな企業活動では、シンプルな基調となる三分法が反対に使用されがちになります。
商品の仕入れや販売を「資産」として考えるか、「費用」として考えるかなどの違いがあるため、勘定科目をしっかり理解しておかないと仕訳に迷いがちになります。
勘定科目の基本をしっかり理解して、どちらでも仕訳ができるようにしておきましょう。