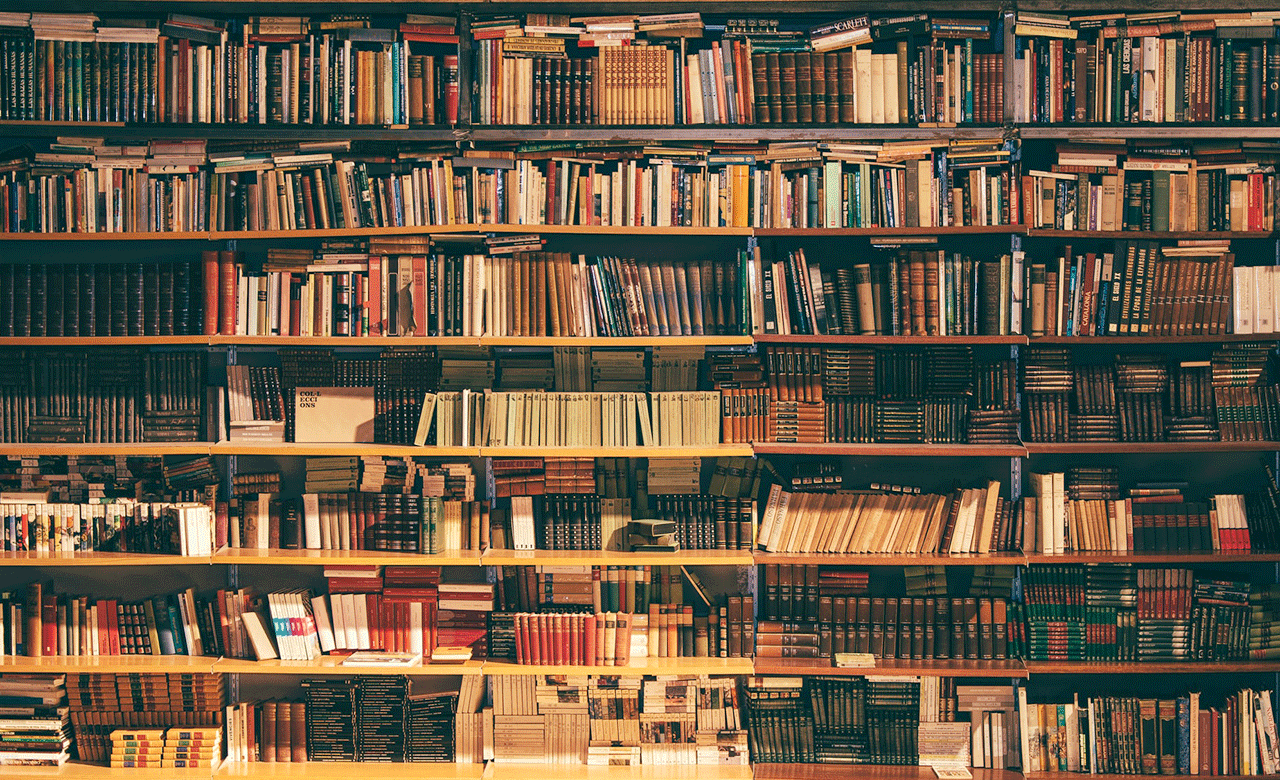Yoshinori
Yoshinori 渋沢栄一の玄孫・渋澤健 著「寄付をしようと思ったら読む本」を独自の解釈でサラッと解説します。
こんな人におすすめ
- お金の使い方を知りたい人
- 毎日の生活に幸福を感じない人
- 仕事のやる気が出ない人
本書の内容はこんな感じです。
- お金は使い方により価値を変える
- 選ぶことにより得られる体験がある
- 他人への投資や寄付でやる気が上がる
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 寄付かぁ。あまりしたことないなぁ。
 Yoshinori
Yoshinori うむ。寄付に対する理解の低さと機会の少なさで、寄付率をGPD比率で見ると日本はかなり低い。
寄付とGDPの比率
- アメリカ:1.44%
- イギリス:0.54%
- 韓国:0.50%
- 日本:0.14%
これには宗教性や国民性とも関係があり、寄付に対して「胡散臭い」や「誠実性を求めすぎる」などが影響しているといわれています。
寄付をするということを習慣化するためには、「寄付する」という行為がボクたちにどのような効果をもたらすのか?ということを知る必要があります。
では、本書を解説します。
お金は使い方により価値が変える
1つ目のポイントは、「お金は使い方により価値を変える」です。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 1万円を投資すると、1年後には1万500円になるとかって話?
 Yoshinori
Yoshinori 違う。1万円を何に使っても1万円の価値しかない。しかし、同じ1万円を使うにしても、達成感や得られる満足感は違うという話だ。
日本の教育では、お金の使い道を2つしか教えていません。
「消費」と「貯蓄」です。
この他にお金の使い道には、「寄付」と「投資」があります。
お金の使い道
- 消費
- 貯蓄
- 寄付
- 投資
寄付以外の3つは「自分のため=me」にお金を使うことで、寄付のみ「私以外のだれか=we」に使う行為です。
自分のためにお金を使うことが悪いわけではありません。
本書でもお金の使い方について、消費→貯蓄の次に、寄付がきています。
あくまでも自分の生活と将来の貯蓄をした上で、余った余裕があれば、投資の前に寄付をすることをすすめています。
投資の前に寄付をすすめるのは、寄付金は投資よりお金がかからず、投資でお金が増えることよりも幸せを感じる時間が長続きするためです。
つまり、メンタル的に投資より寄付の方が費用対効果が高いためです。
毎月100円を寄付して、1ヶ月ずっと社会貢献していることに満足できるなら、その100円は缶ジュース一本よりあなたの生活をより充実したものにしてくれます。
選ぶことにより得られる体験がある
2つ目のポイントは、「選ぶことにより得られる体験がある」です。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん プレゼントも選んでいるときが一番楽しいもんね。
 Yoshinori
Yoshinori そうだな。プレゼントも寄付も同じで、誰かのことを思い浮かべながら前向きな行動をすると、何ももらっていないのに人は幸福を感じることができる。
本書の1番の特徴は、寄付する先を調べて自分で選ぶことを推奨している点です。
寄付というと、街中で見かける募金活動やコンビニなどに設置している募金箱です。
しかし、偶然見つけただけの募金箱にお金を何も考えずに入れるのは、もったいないと著者はいいます。
国際社会には、貧困や森林伐採、難病、戦争被害などあらゆる社会問題あります。
そういった社会問題に対して、自分のできること何なのか?誰のどんな状況を救いたいと思うのか?寄付する団体を探して、選ぶことでそういった社会問題にも前向きに接することができるようになります。
寄付をする先を選ぶことで、自分のためだけにお金を使うこと以外で得られる体験をしてみましょう。
他人への投資や寄付でやる気が上がる
3つ目のポイントは、「他人への投資や寄付でやる気が上がる」です。
先にも説明したように、自分以外の誰かのことを思い行動をすることで、人は幸福をことができます。
頑張っている人を支援したり、困っている人に手を差し伸べることで、普段の生活や仕事にもやる気があふれるようになります。
高価な貴金属や欲しいものを手に入れても人の幸福感は続きませんが、他人への投資や寄付は自分が手を差し伸べた人の活躍を見るたびに幸せな気分になるので、幸福の効果は長続きします。
他人のためにお金を使うことで、今まで知らなかった体験や繋がりができるかもしれません。
まとめ
- お金は使い方により価値が大きく異なる
- 選ぶことにより得られる体験がある
- 他人への投資や寄付でやる気が上がる