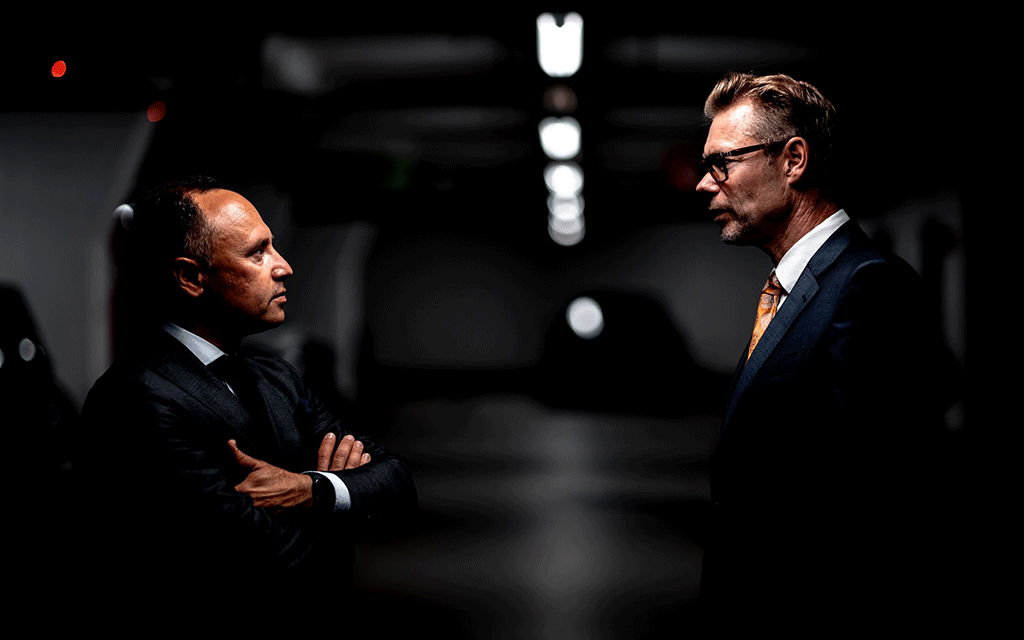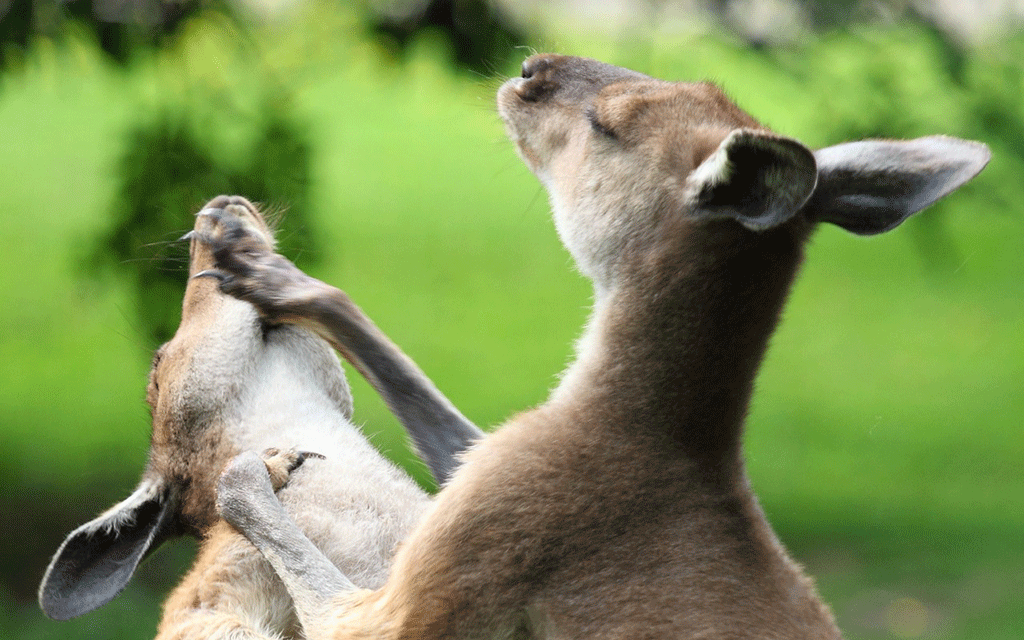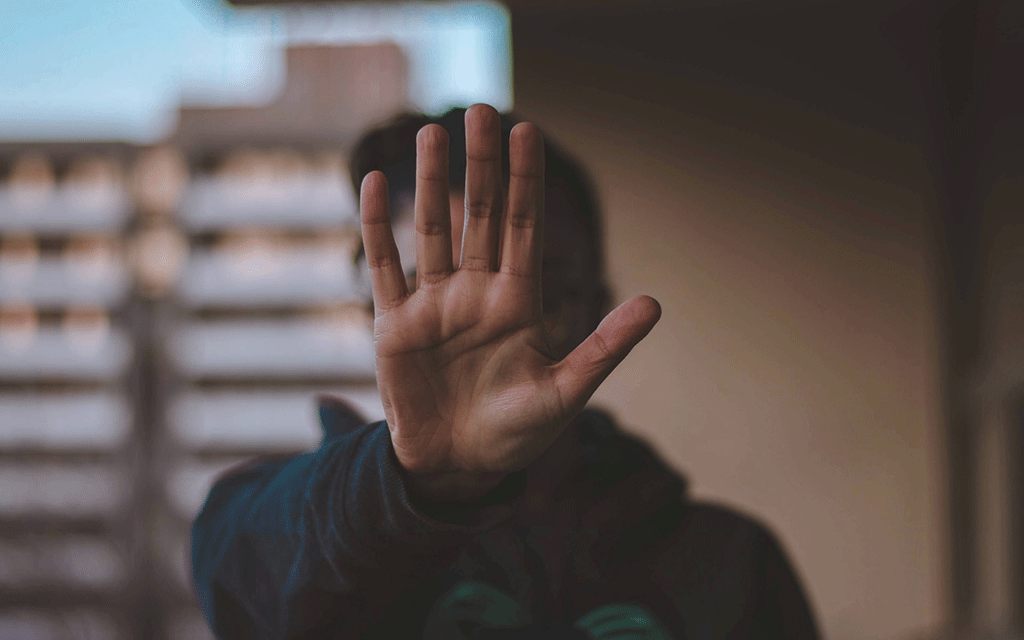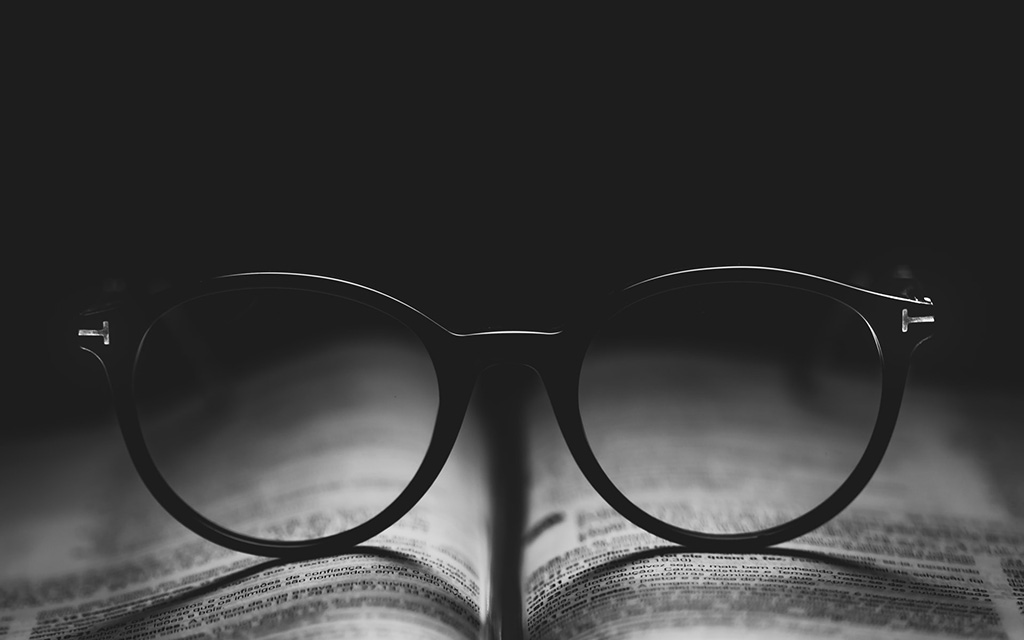気の散りやすい人は、仕事や勉強、趣味など何をしても長続きしません。
理由は、他の人よりも「飽きやすい」性質を持っているからです。
飽きやすい性質を持っていると、
経営陣の頭が固い
給与が安い
足の引っ張り合いばかりしている
などの社内のウワサ話に流され、
「自分が評価をされないのは、会社が悪い」
と、思い込むようになり、仕事へのやる気を失います。
そして、転職すれば抱えている問題のすべては解消され、幸せになれると思い込み、仕事をコロコロ変えてしまいます。
 Yoshinori
Yoshinori 残念だが、仕事を変えても問題は解消されない。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん どこの会社も同じってこと?
 Yoshinori
Yoshinori 本人の性質が変わらないからだ。
転職を繰り返す人は、どこの会社に行っても外からの影響を強く受けてしまうため、今の環境に不満を抱え転職を繰り返します。
飽きっぽい性質を持っている人が幸せになるには、その性質を活かした生き方をする必要があります。
この記事では、仕事が長続きせずに転職ばかりを繰り返す飽きっぽい性質を持っている人に向けて、散漫な注意力を活かす方法について解説をします。
飽きやすい理由と仕事を続ける方法
飽きっぽい性格の原因は、遺伝です。
見た目や運動神経と同様に、性格も遺伝するからです。
職人気質の親の子供は、コツコツ努力を続ける職人気質な性格になります。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 遺伝なら、直せないね。
 Yoshinori
Yoshinori そんなことはない。性格の半分は遺伝で決まるが、もう半分は環境で決まる。
飽きっぽい性格の人でも、定年まで仕事を続けられる人はたくさんいます。
そのために必要なのが、「環境」です。
一つの仕事を続けたいなら、続けるための環境を用意すれば仕事を続けることができます。
たとえば、
一人暮らしをする
結婚する
子供を作る
家を買う(借金を作る)
起業する
など、仕事を辞められない環境を用意すれば、仕事を続けることができます。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 仕事のために、借金を作るの?
 Yoshinori
Yoshinori 理由もなく続けられる性格でなら、借金は必要ない。出来ないなら、環境を用意すべきだ。
そうすることで、感情に任せた判断ができなくなり、駆り立てられるように仕事に向かうことができます。
飽きやすい人の特徴
飽きっぽい性格をサポートするためには、環境を用意することがベストです。
しかし、そのために借金をしたり、起業をするのはリスクが高いため、飽きやすい性格を活用する方法を解説します。
飽きの正体
飽きの正体は、「慣れ」です。
仕事などに慣れるとつまらないと感じるようになり、飽きてしまいます。
飽きっぽい性格の人は、遺伝的に仕事や趣味などに順応する能力が高いため、すぐに慣れてしまい、つまらないと感じるようになります。
はじめて行う仕事も1回2回体験すれば、すぐにコツを掴めてしまいます。
コツが掴めるため、その後の仕事は作業となり面白くなくなります。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 飽きっぽい人って優秀なんだね。
 Yoshinori
Yoshinori 優秀だが、すぐにできるから器用貧乏になり下がる。
人は手に入れるものが困難であればあるほど、そのものに固執します。
飽きっぽい性格の人は、すぐに出来ることが多いため、できることに固執しません。
そして、できることに固執しない飽きっぽい性格の人は、新しいことに興味を持ちやすいという性質があります。
開拓者魂を活かす
飽きっぽい性格を仕事で活かすには、外部からの刺激に弱いという弱みと強みに変える必要があります。
外部からの刺激に弱いため、注意散漫になりがちな飽きっぽい人は、新しいことにも挑戦する「開拓者魂」を持っています。
社内の新しい企画やこれまでとは違った方法で仕事をアプローチしたりなど、他の人が普段しないようなやり方を平気で採用して結果を出すことができます。
普段の仕事を工夫したり、新しい仕事の話に飛びつくことで、仕事への慣れを緩和させ、仕事=つまらないという方程式を崩すことができます。
好きを仕事にしない
飽きっぽい人がもっともしてはいけないことは、好きなことを仕事にすることです。
人は嫌いなものより好きなものに取り組む時間が長いため、慣れて飽きるのが早くなります。
飽きっぽい人が好きなことを仕事にすると、短期間で興味の対象が移るため、好きなことを仕事にするのはおすすめできません。
好きではないけれど、得意なことを仕事にするのがベストです。
人は好きではないけれど、説明が得意であれば営業をする。
細かい作業は好きじゃないけれど、計算が速ければ経理をする
といった感じです。
好きではないけれど、新しいやり方を自分なりに工夫をし続けることができる得意なことをすれば、仕事を長く続けることができます。
まとめ
- 飽きやすい性質を持っている人は、仕事も趣味も長続きしない
- 仕事は環境をセットにすることで、続けられる
- 飽きの正体は、「慣れ」
- 慣れ=つまらない
- 新しいことに目を向ける
- 好きなことを仕事にしない
- 得意なことを工夫しながら仕事をする