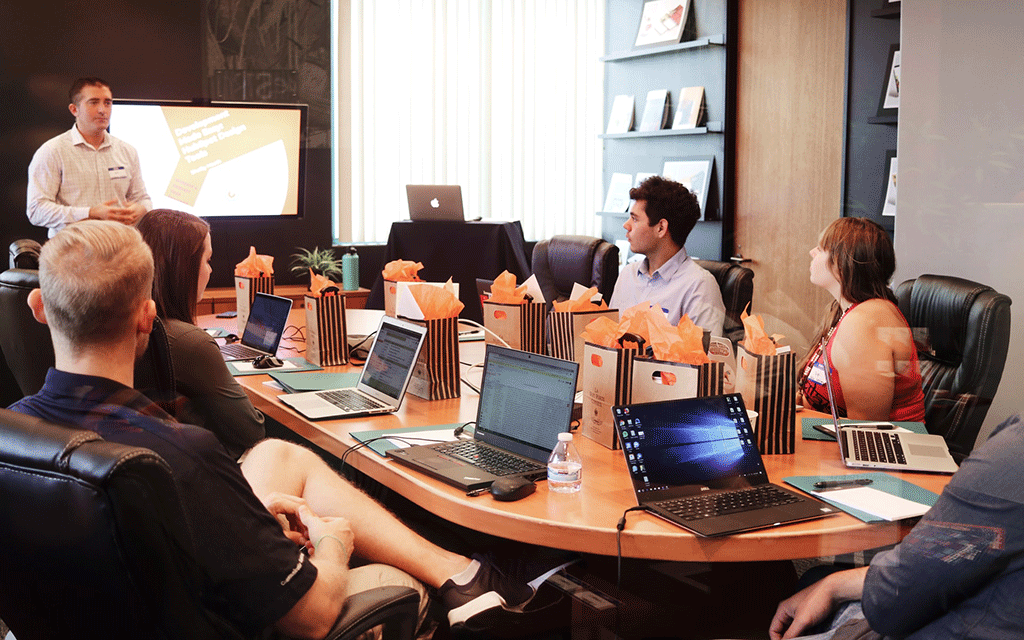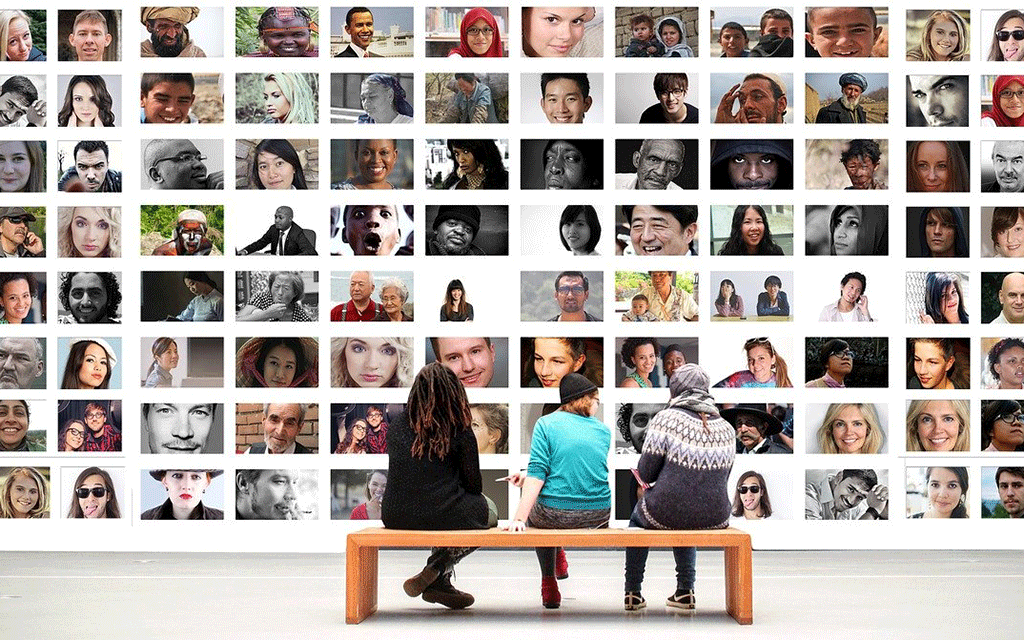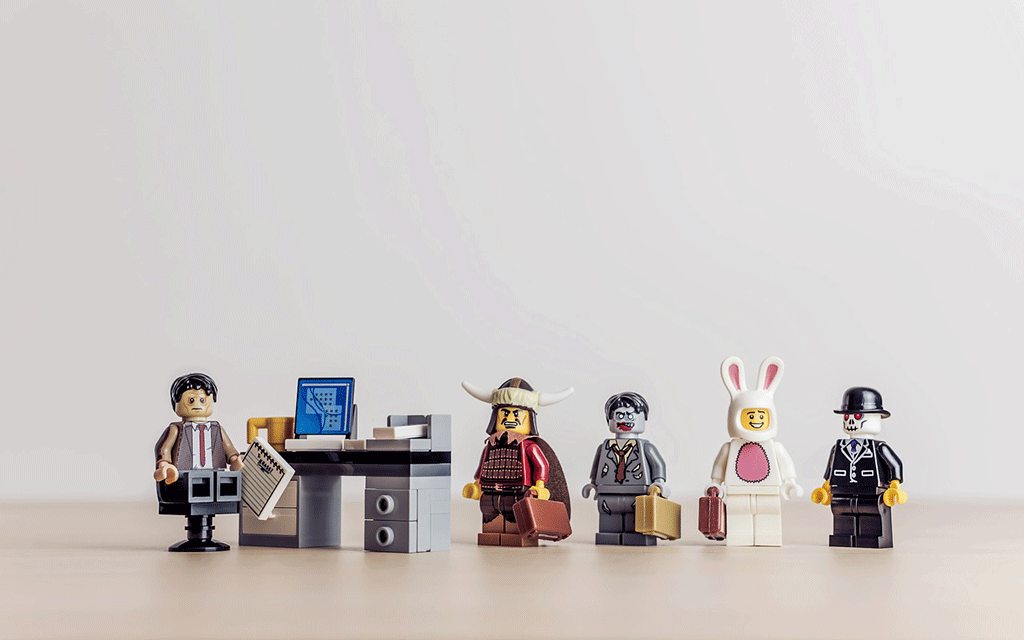アシのMちゃん
アシのMちゃん 法人(会社)が支払っている税金ってどうやって処理しているんですか?
こんな人のための記事です。
日本にはたくさんの税金があります。
- モノを購入・消費するとかかる税金
- モノを所有・使用しているとかかる税金
- 儲ける(所得)とかかる税金
法人が儲けるとかかる代表的な税金には、法人税、住民税、事業税の3つがあります。
簿記の世界では、これらをまとめて「法人税等」といいます。
法人税などには、それぞれ「仕訳」「納付」「納税」のタイミングがあります。
 Yoshinori
Yoshinori 今回の記事では、具体的な仕訳例をもとにして実際の処理の仕方をご紹介します。
では、解説をはじめます。
法人税等の仕訳タイミング
法人税は、企業活動によって得られた所得(儲け)に対して課される税金です。
法人の所得とは、会計上のすべての利益ではなく、利益から損益を引いた金額(税引前当期純利益)から計算を行います。
法人税は、この税引前当期純利益に税率を乗じて算出します。
式にすると、こんな感じです。
式)支払う法人税等=税引前当期純利益×税率
 Yoshinori
Yoshinori 税引前当期純利益は、すべての決算整理仕訳を作成した後の「損益」勘定のこと。
なので、法人税等の仕訳は、期末決算後(決算整理仕訳を作成した後)にまとめて行います。
計算問題.
法人税等以外の決算整理仕訳を作成した結果、損益勘定残高が100万円となった
法人税などの税率を40%にしたとき、支払う税金は?
答え.
40万円納税する
 Yoshinori
Yoshinori 損益勘定の残高は100万円となっていますが、実際の儲けは60万円となります。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 税金ってまとめると高いですね。
法人税等の仕訳の流れ(具体例)
例題1-1.
令和元年に会社を起業し、期末日を毎年3月31日とした
令和2年3月31日が終了し、初めての決算をした結果、損益勘定残高は1,000万円であった
法人税等の税率を40%としたときの決算整理仕訳は?
(借)法人税等4,000,000(貸)未払法人税等4,000,000
例題1-2.
令和2年5月31日に未払法人税等を小切手で納税した
(借)未払法人税等4,000,000(貸)当座預金400,000
例題1-3.
令和2年11月30日、法人税の暫定金を小切手で前払いした
(借)仮払法人税2,000,000(貸)当座預金2,000,000
例題1-4.
令和3年3月31日、税引前の損益勘定残高は2,000万円であった
法人税等の税率は40%
(借)法人税等8,000,000(貸)仮払法人税2,000,000
(貸)未払法人税6,000,000
例題1-5.
令和3年5月31日に未払法人税を小切手で支払い、11月30日には暫定金を小切手で前払いした
(借)未払法人税等6,000,000(貸)当座預金600,000
(借)仮払法人税4,000,000(貸)当座預金400,000
・
・
・
 Yoshinori
Yoshinori 法人税の支払いはこれの繰り返し!
期中に納税し、中間で前払いする
先程の例題で気づかれた方もいるかと思いますが、法人税は期中に2回支払います。
1回目の支払いは、前期の決済算出した「未払法人税等」の支払いです。
この支払いは原則として決算日から2ヶ月以内(大企業は3ヶ月以内)に納付する義務があります。
例題の決算日は3月31日であるため、納付期日は5月31日です。
2回目の支払いは、当期の暫定的な法人税「仮払法人税」の支払いです。
仮払法人税は、期首から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内に、前年度の法人税の半額を支払います。
例題の期首は4月1日であるため、11月30日が納付期限となります。
これが中間で前払いする法人税等です。
あとは、決算で算出した実際の法人税等と前払いした法人税等を算出し、これを期中に納税にし、また決算で算出した半分の額を前払いしていきます。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん これの繰り返しですね!
まとめ
法人が支払う法人税等について解説をしました。
法人税には「法人税」「住民税」「事業税」の3つがあり、これらをひとまとめに「法人税等」といいます。
法人税等は期末決算後の損益勘定残高をもとに算出し、決算後の2ヶ月以内に支払い、前年の半額を期中に前払いします。
利益や儲けにかかる税金は、自分で利益を確定させて、自分で税額を確定し、自ら税務署に申告、納税する義務があります。
そのため少しだけズルをしようと思いがちですが、お金より信用のほうが大切です。
信用を失わないよう、真面目にコツコツ税金も支払いましょう。