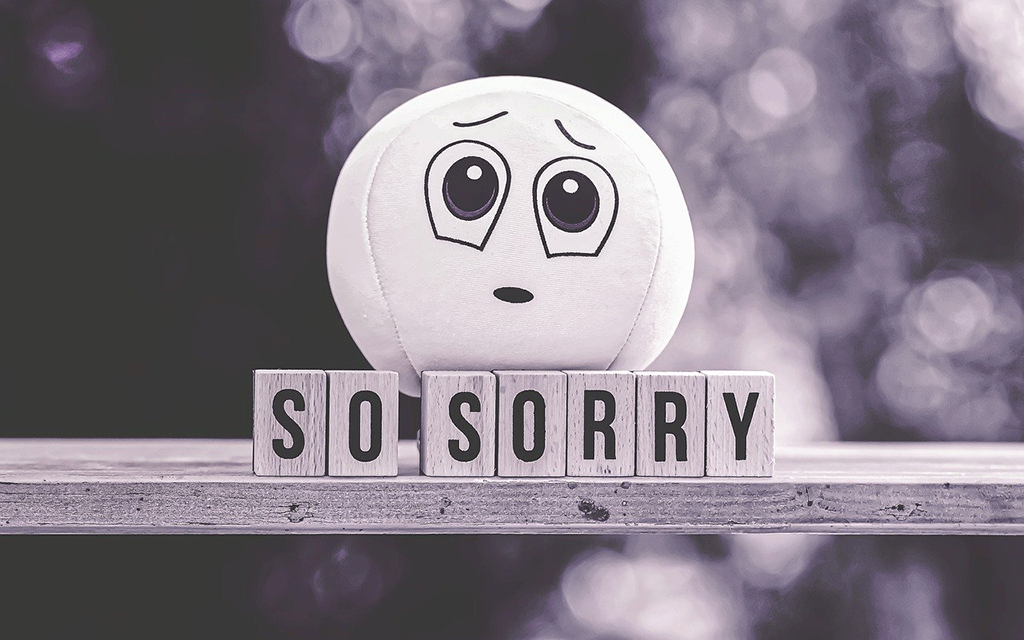アシのMちゃん
アシのMちゃん 三文法で仕訳した売上総利益と売上原価って、どうやったらわかるんですか?
こんな人のための記事です。
帳簿で仕訳をした「売上」には、「商品売買によって得た利益」と「その他の取引で得た利益」の2通りあります。
「その他の取引で得た利益」に関しては、勘定科目がそのまま使えるため何の問題もありません。
しかし、三文法で仕訳した「商品売買によって得た利益」に関しては、売上総利益や売上原価はわかりません。
この時点で
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 何のこと?
 Yoshinori
Yoshinori この記事で覚えることは「シークリクリシー」だけ!
ということで、この記事では
- 簿記3級試験に合格するために最低限必要なことを覚える
について、まとめていきます。
理屈はわからなくても、とりあえず結論だけ覚えてもらえれば大丈夫です!
三分法の売上原価の算定とは?
三文法で仕訳したときの売上総利益や売上原価がわからないという話をしていますが、これがそもそも何のことを言っているかについてまず解説をします。
簿記の仕訳には「三分法」と「分記法」があります。
分記法で商品売買の仕訳を行うと、以下のようになります。
例題1.
現金100円で仕入れた商品を300円で売買した
(借)現金300(貸)商品100
(貸)商品売買益200
分記法では、売上原価(100円)と売上総利益(200円)がすぐにわかります。
一方、これを三分法で仕訳するとこうなります。
例題2.
現金100円で仕入れた商品を300円で売買した
(借)仕入100(貸)現金100
(借)現金300(貸)売上300
この例題では売上原価(100円)はわかりますが、売上総利益(200円)を仕訳していないのではわかりません。
さらにこうすると、売上原価もわからなくなります。
例題3.
2019年3月に100円で仕入れた商品を2019年4月に300円で売買した
2020年3月31日に期末が終了した
(借)現金300(貸)売上300
簿記のルールでは、当期の仕訳のみ記帳を行うため、商品売買で得たときの売上原価がわからず、売上総利益もわかりません。
では、どうするのか?
結論:シークリクリシーと覚える
結論としては、決算整理仕訳で仕入勘定の仕訳する必要があります。
例題4.
期末商品棚卸高が100円で、当期商品棚卸高が200円分のときの仕入仕訳は?
(借)仕入100(貸)繰越商品100
(借)繰越商品200(貸)仕入200
このように仕訳勘定を行うことで、売上原価(100円)と売上総額(200円)がわかります。
この辺りのことを簿記3級で理解するのは難しいので、
(借)仕入(貸)繰越商品 ← 期末商品棚卸高
(借)繰越商品200(貸)仕入200 ← 当期商品棚卸高
上記の仕訳を左上の頭文字から「シークリ、クリシー」と覚えて仕訳をすれば大丈夫です。
 Yoshinori
Yoshinori 正しく理解を深めたい人は、簿記の参考書を読んできちんと理解しましょう。
まとめ
商品売買の算定に関するかんたんな仕訳方法について解説をしました。
商品売買の仕訳は、分記法であれば一目で仕訳内容も分かります。
しかし、三分法では売上総利益はわかりません。
さらに、売れた商品の仕入れが当期のものとは限らないため、三分法で仕訳をしただけでは売上原価もわからないといった場合があります。
そうしたときは、決算整理仕訳で期末商品棚卸高と当期商品棚卸高を「シークリ(期末商品棚卸高)クリシー(当期商品棚卸高)」と仕訳をすることで、「売上総利益」と「売上原価」を算出することができます。
一息にすべてを理解することは難しいので、まずは処理の仕方を覚えて、仕訳に慣れてきたらどう言った理屈なのか?じっくり取り組んでみてください。