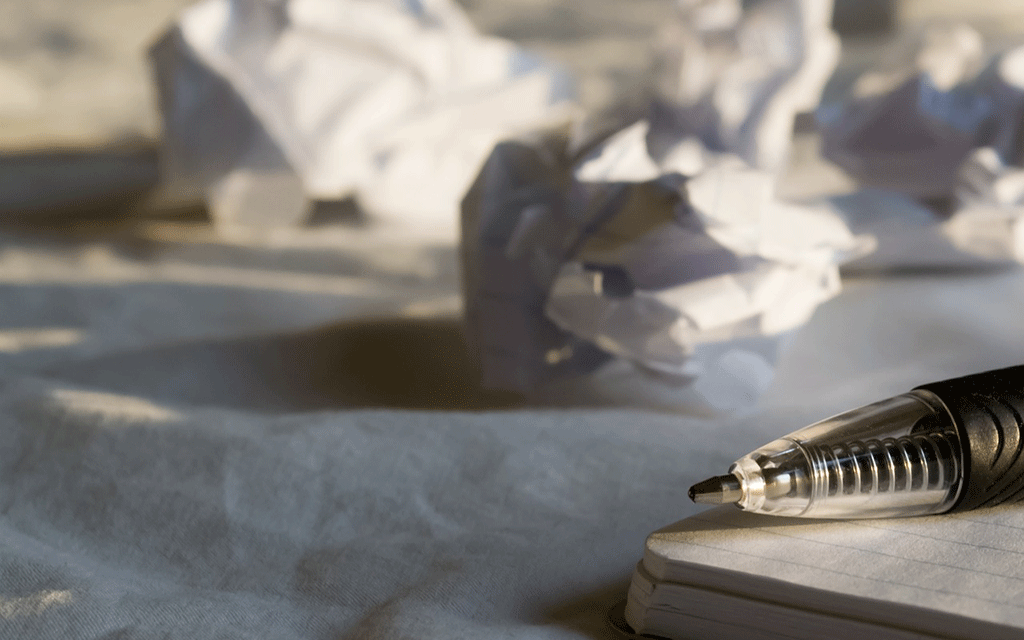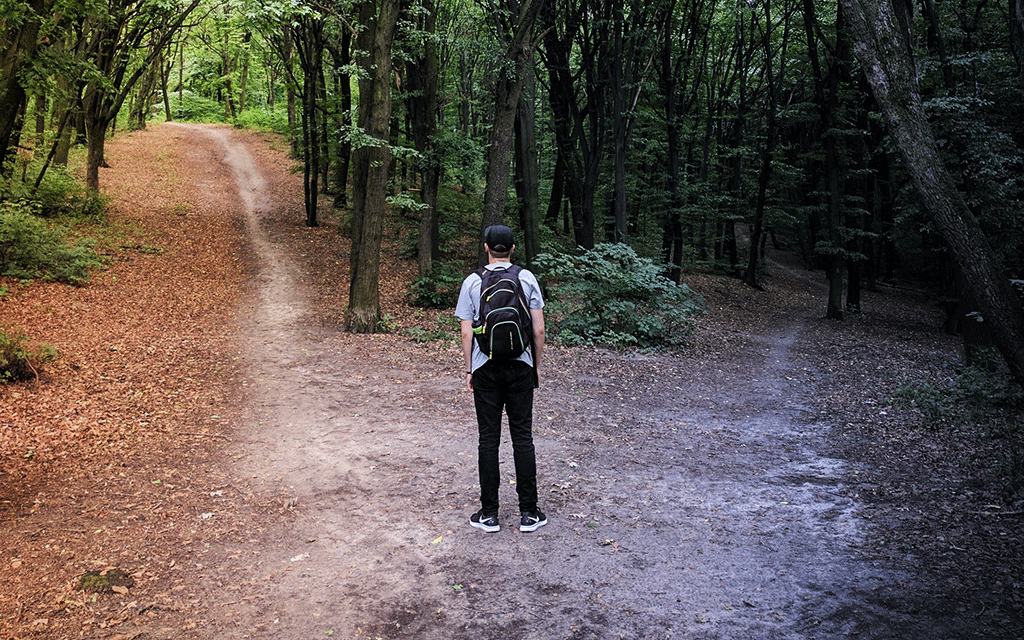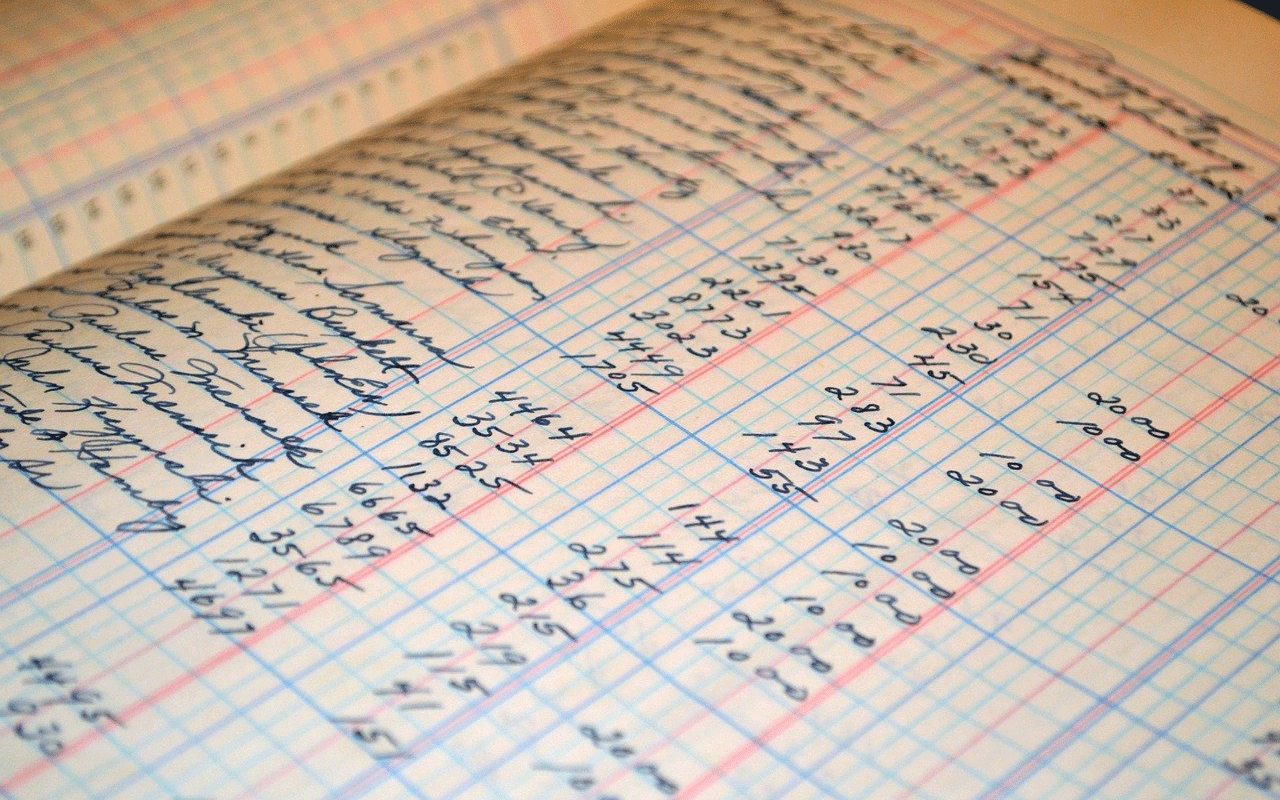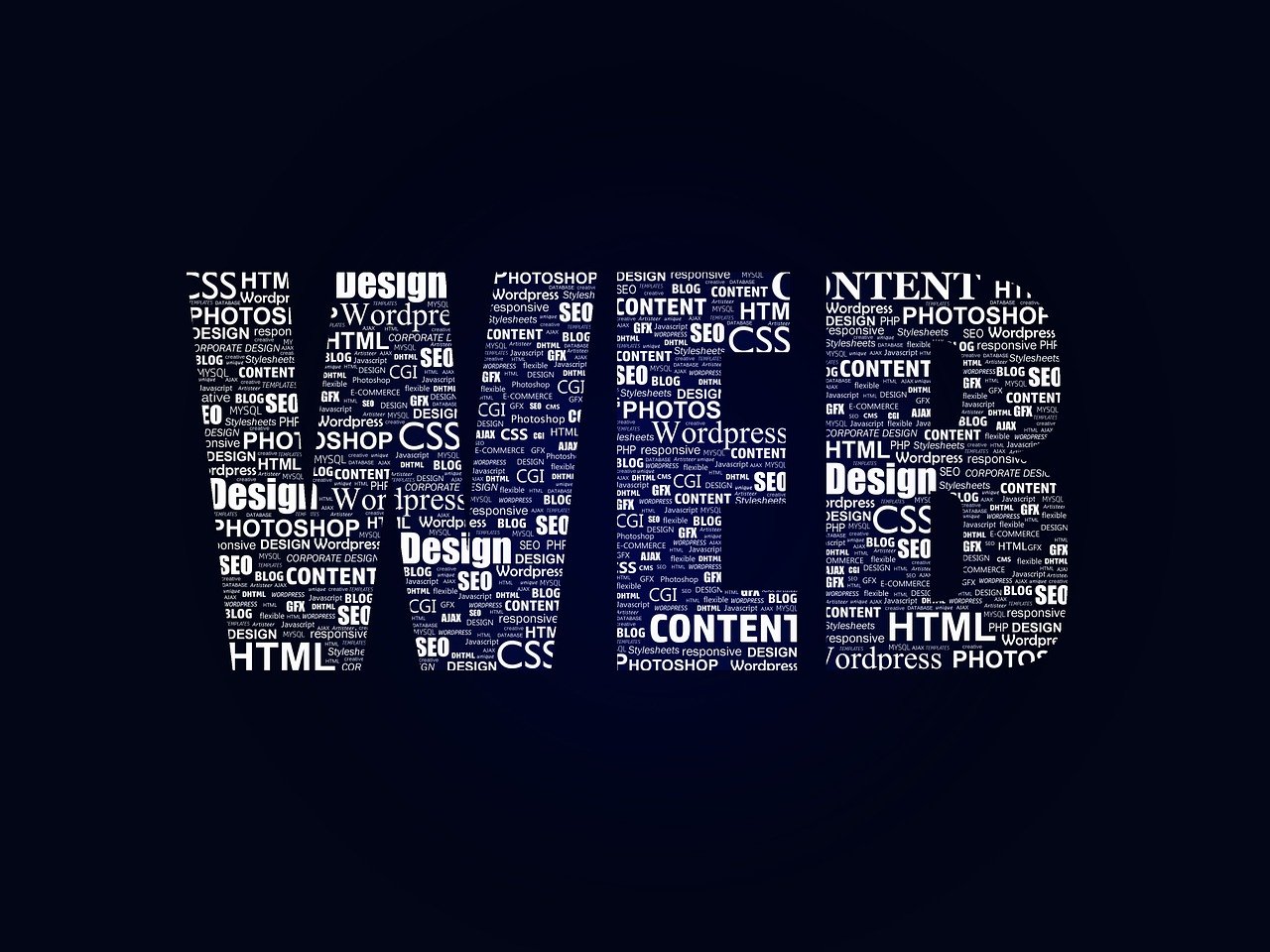アシのMちゃん
アシのMちゃん 消費税の仕訳と納税ってどうすればいいですか?
こんな人のための記事です。
結論から言うと、
 Yoshinori
Yoshinori 消費税の仕訳はその都度必要で、期末後と期中に納税します。
となります。
日本の税金は、だいたい3つに分類されます。
- モノを購入・消費するとかかる税金
- モノを所有・使用しているとかかる税金
- 儲けるとかかる税金
モノを購入・消費するとかかる税金には、消費税や不動産取得税、自動車取得税、たばこ・酒税などたくさんあります。
この記事では、仕訳回数が圧倒的に多い「消費税」の仕訳方法と納税について解説していきます。
消費税の仕組み
消費税の仕訳を見ていく前に、その仕組みについて解説をします。
消費税はモノを購入するときにかかる税金です。
そのため税金を支払うのは、「消費者」です。
しかし、税務署に税金を納めるのは、「モノを売った事業者」になります。
事業者は消費者から一時的に預かった税金を消費者の代わりに納税します。
このため、消費税は「間接税」といわれます。
モノを売った事業者も売るモノを仕入れる際に、卸業者や生産者に消費税を支払います。
消費税は、モノを売った・買ったときの差額を税務署に納付することになります。
これが消費税の納付の流れです。
消費税の納付の流れ(仕訳する人:モノを売った事業者)
- 事業者が卸業者から商品を仕入れる
- 商品代金と一緒に消費税を支払う
- 消費者に商品を販売する
- 消費者から税金(消費税)を預かる
- 預かった税金を税務署に納付する
 Yoshinori
Yoshinori 消費税の仕組みは、こんな感じです。
消費税の仕訳
例題1-1.
あるコンビニの店主が税抜300円の商品を掛けで仕入れた
(借)仕入300(貸)買掛金330(借)仮払消費税30
このときの仕訳のポイントは、仕入勘定に消費税30円を加えないことです。
ちなみに、消費税を支払うときの勘定科目には、「仮払消費税」という費用みたいな「資産」の勘定科目を使います。
例題1-2.
上記で仕入れた商品を500円(税抜)で販売した
(借)売掛金550(貸)売上500
(貸)仮受消費税50
消費税を受け取ったときの勘定科目には「仮受消費税」という「負債」の勘定科目を使います。
例題2-1.
事務所の作業机を税抜き4万円で現金購入した
(借)備品40,000(貸)現金44,000
(借)仮払消費税4,000
 まい
まい 期中はこの消費税の仕訳を毎回するんですね。
消費税の決算整理仕訳
モノを購入・販売するごとに仕訳する消費税は、1年間繰り返すと山のような金額になります。
山積みされた仮受・仮払した消費税の差額を決算整理仕訳で求めて、その差額を決算後2ヶ月以内に税務署に納付します。
 Yoshinori
Yoshinori 大企業の場合は3ヶ月以内!
例題3-1.
決算になったので、期中で支払った消費税と受け取った消費税を整理した
仮払消費税は500万円、仮受消費税は700万円であることがわかった
このときの決算整理仕訳は?
(借)仮受消費税7,000,000(貸)仮払消費税5,000,000
(貸)未払消費税2,000,000
処理としては、仮受・仮払消費税をそれぞれ借方と貸方にわけて相殺してゼロにします。
あまった差額の200万円が納付する消費税となります。
例題3-2.
上記で算出した納付すべき消費税を
5月20日に小切手で振り出して支払った
(借)未払消費税2,000,000(貸)当座預金2,000,000
これで消費税の支払いは完了です。
まとめ
簿記会計における「消費税」の仕分けについて解説をしました。
事業者にとっての消費税は、消費者から仮に預かった税金と自分が支払った税金の差額分を支払う間接税です。
売買するたびに発生する消費税は、期中の仕訳で鬼のように仕訳し、期末には山のような金額になっています。
期末の決算整理仕訳で算出した消費税は、次の期首の2〜3ヶ月以内に納付すべき義務となっています。
実際に消費税を支払いにいくケースは少ないかもしれませんが、普段何気なく支払っている消費税はこうして納付されています。
参考になればうれしいです。以上!