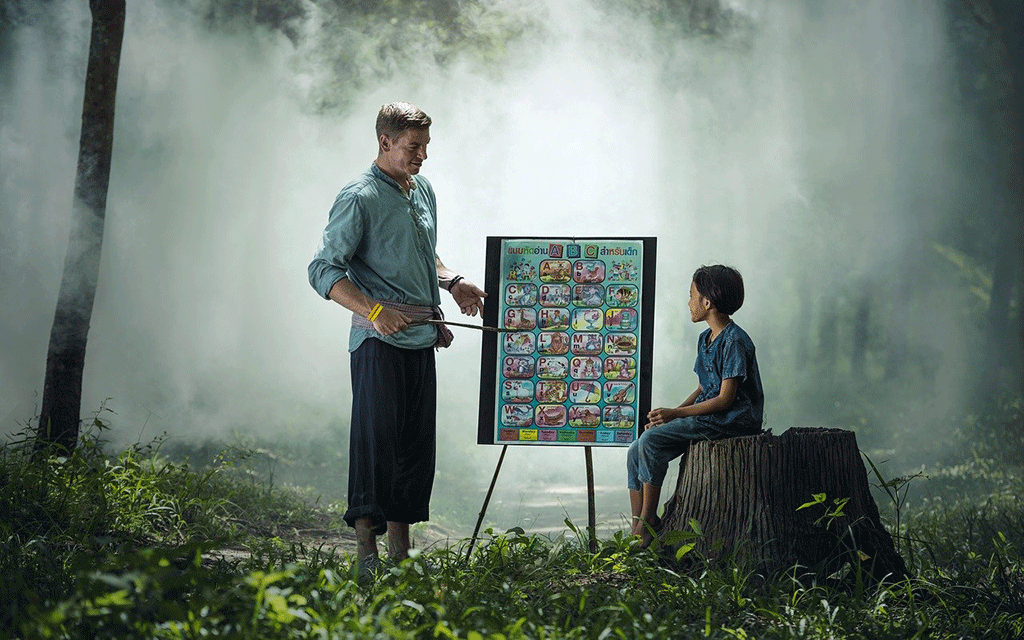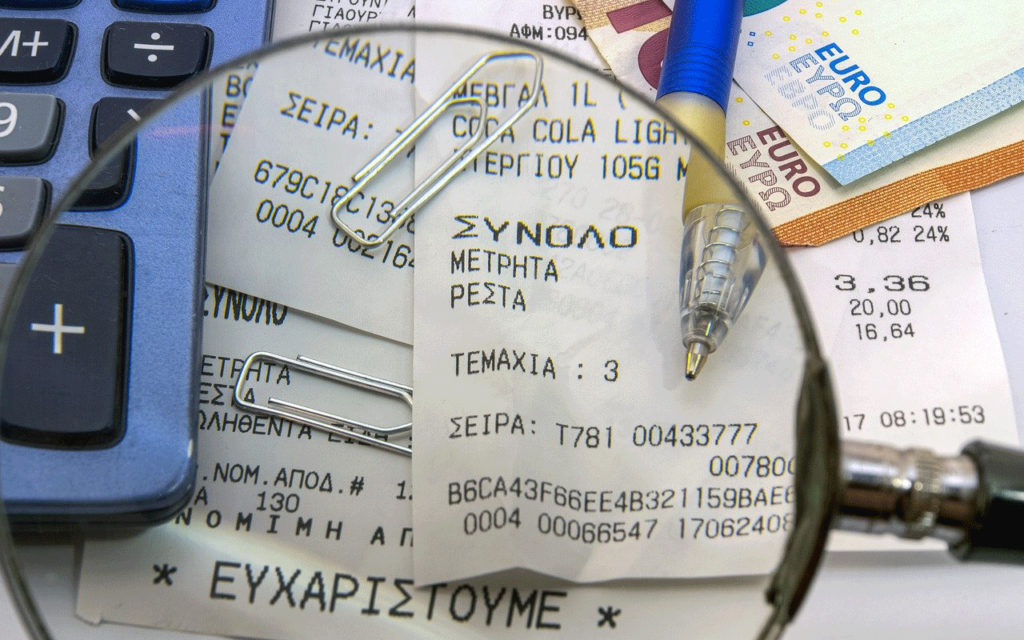
こんな人におすすめ
- 証憑の元にした仕訳がわからない
- 仕訳に必要な証憑を知りたい
- それぞれの証憑の意味を知りたい
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 「納品書」って何で必要なんですか?
 Yoshinori
Yoshinori 発注した商品と納品された商品を照合するためだよ。どうしてそんなことが気になるの?
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 経理に「納品書」と「請求書」を持っていくと、「納品書はいらない」って冷たく言われるんですよ。
 Yoshinori
Yoshinori 納品書は税務上必要な書類ではないから、仕訳するだけならいらない」っていわれるかもね。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 紛らわしいから送ってこないでほしいんですけど。
 Yoshinori
Yoshinori 納品する側にとっては、商品やサービスを納品した証明になる証憑となるから、納品書や検収書を出す会社は多いと思うよ。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 証憑?
証憑って何?
証憑は、取引や契約が両者の同意で成立したことを証明する書類です。
証憑には領収書や小切手、約束手形、納品書、請求書など取引の証拠となる書類のほかに、稟議書や雇用契約、退職届など取引を説明する証憑があります。
この記事では、簿記会計に関係する証憑の種類やその取り扱いについて解説をします。
証憑の種類
簿記では問題文を中心に仕訳をおこないますが、実際の現場では請求書や領収書などの証憑を基に仕訳を行います。
ここでは簿記会計の仕訳で使用する代表的な証憑を5つご紹介します。
- 見積書
- 発注書
- 納品書
- 請求書
- 領収書
それぞれの特徴と役割
見積書
外部との取引において、見積書の発行は対応しておくべき書類の1つです。
受注先(請負業者)にとっての見積書は、納品予定と業務内容、金額を発注先(依頼主)に提案する書類となります。
これらを明記することで、依頼主との認識の違いをなくし、後のトラブルを抑制します。
依頼主にとっては他の業者との比較検討の材料にしたり、また会社の決議を仰ぐりん議書に添付する書類として活用したりします。
経理の仕訳では、請求書の内容が誠実に正しく行われた取引であることを説明する書類として、稟議書とあわせて確認を行います。
 Yoshinori
Yoshinori 見積書の取り扱いは会社のルールによって異なります。
発注書(注文書)
発注書は商品やサービスを発注(注文)する時に発行する書類の1つです。
実際には、発注書を発行せずに口頭で進めることもありますが、公正取引委員会では、「親事業者は発注に際して具体的記載事項をすべて記載している書面(3条書面)を直ちに下請事業者に交付する義務がある」としています。
また、見積書や発注書は、これだけでは正確な取引金額を表す証憑(種類)とは認められないため、支払い時の請求書とセットにして保管をしましょう。
納品書
納品書は、依頼主に納品する商品明細を記入した書類です。
納品書の主な役割は、依頼主と請負業者の両者間で納品漏れによるトラブルがないことを確認するためです。
そのため、仕訳を担当する経理には必要でない書類として扱われることもあります。
ただし、納品した・されたことを証明する証憑であるため、一定期間は請求書の写しと一緒に保管するなど後々トラブルにならないよう注意しましょう。
また、納品書と似たような書類に「検収書」があります。
検収書は請負業者から納入された商品や数量、金額に謝りがなく適切であることを依頼主が点検したことを証明する書類です。
納品書と似たようなものですが、いったん検収書をだしてしまうと、例外をのぞいて、それ以後商品やサービスに関するクレームを主張できなくなります。
検収書は納品書や受領書とは異なるため、取り扱いに注意しましょう。
請求書
請求書は、商品やサービスなどを納品した後、依頼主に支払いをしてもらうための金額や締め日を記載した書類です。
請求書の発行タイミングは納品と同時に行う「都度方式」ともしくは納品してその後に一括で請求する「掛売方式」があります。
都度方式
都度方式は、納品ごとに請求書を発行する方式です。
代金回収を迅速に行えるメリットがある反面、請求書発行に手間がかかります。
掛売方式
掛売方は、締め日を設定して月に1度請求する方式です。
毎月の取引回数が多い場合や定期的に取引がある場合などに適しています。
領収書
領収書は、代金を受け取った際に発行する書類です。
商品やサービスを提供する側にとっては、対価を代金として受け取ったことを証明になり、お金を支払った側にとっては、商品代金を支払った証明になります。
経理の仕訳では領収書ではなく、レシートでも仕訳を行います。
経費精算をする場合は、レシートに使用用途と責任者印があれば経費として認めてもらえます。
逆にこれがない場合は、経費として認められないこともあります。
まとめ
経理の仕訳に必要な「証憑」について解説を行いました。
証憑は、サービスを提供、または提供される両者の間で合意がなされたことを証明する書類です。
それぞれの意味をきちんと理解して、正しく対処してきましょう。