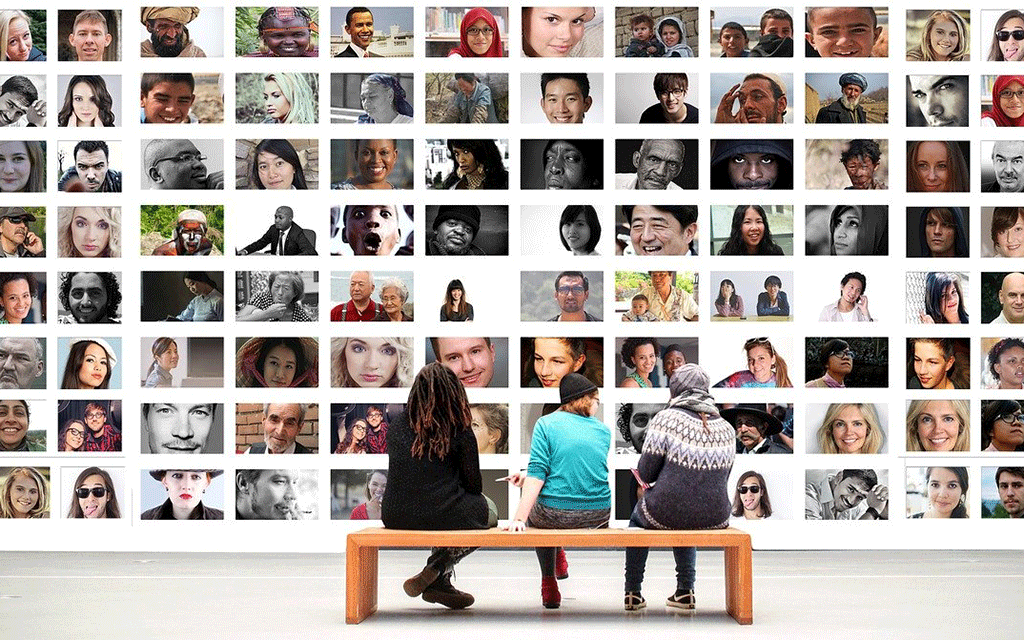アシのMちゃん
アシのMちゃん 説明がわかりにくいって言われます。筋道を立てて説明するコツってないですか?
上司やクライアントに仕事の内容や進捗、結果をわかりやすく説明することはビジネスでは必須のスキルです
むしろ説明さえ上手にできれば
「あいつ仕事できるな」
と、まわりの人の評価が上がります
しかし多くの人は
「雑談はできるけど、説明は苦手・・・」
という人がほとんどです
 Yoshinori
Yoshinori 飲み会や喫煙スペースでは元気だけど、オフィスでは元気のない人が多い
今回はわかりやすい説明で、相手に納得してもらうための話し方のコツについて解説をします
わかりやすい説明のコツ1:「例え話」を使う
説明が上手な人は、難しい話を短く簡単に説明できます
説明が下手くそな人は、簡単な話を難しく話します
なぜ、ボクたちはわかりやすく説明できないのか?
結論は
例え話が下手くそ、もしくは例え話を使わない
からです
説明な上手な人は、例え話が上手です
話の長い人のことを例えるときに
説明の上手な人は、
「部長の話は、校長先生みたいに長い」
と例えます
一方、説明が下手くそな人は、
「部長の話は、エンジニアみたいに話が長い」
と例えます
説明が上手な人が誰もが馴染みのあるもので例えるのに対し、説明が下手くそな人は、マニアックなモノで例えるため、相手に話の内容が伝わりません
説明上手になるためには、誰もが体験したことのあるような”あるあるネタ”を織り交ぜて例えると短くわかりやすく説明することができます
わかりやすい説明のコツ2:ストーリー仕立てに話す
わかりやすく説明するためには、時系列をきちんと追って説明することが大切です
時系列を追わないで話をすると
いま何の話をしているのか?
話し手も聞き手も迷子になってしまいます
時系列に話をするコツは、「ストーリー仕立て」にすることが大切です
お笑い芸人の「すべらない話」のように過去に起こった出来事をストーリー仕立てに話をすることにより、わかりやすく話をすることができるようになります
また、自分の過去の経験をストーリー仕立てに話をすると、感情と論理が一緒になるため、相手の記憶に強烈残ります
そうすることで
「あの人の話は面白い」
「あの人の話はわかりやすい」
と、思われるようになります
話をわかりやすく伝えるためには、話の内容を要約して一部分だけを抜き出すより、ストーリー仕立てに話すことの方がわかりやすく相手に伝えることができます
わかりやすい説明のコツ3:定義を説明する
話を短くするために、専門用語を多用する人がいます
専門用語を使うこと自体は、悪いことではありません
冒頭のように細かい定義を説明しなくてよいため、本題に入る前に時間を費やすことがありません
しかし、関係部署以外やクライアントなど自分と異なる領域の人とコミュニケーションを取る必要のある場では、専門用語を使うことに注意が必要です
聞き手が専門用語を理解していない、もしくは定義を曖昧に理解している人が多いからです
専門用語の定義を簡単に短く説明できると
「コイツわかっているな」
と、聞き手に緊張感を持たせることができるため、会議参加者の聞く姿勢が整います
専門用語やカタカナ言葉を本題の前に明確するのは面倒ですが、定義が曖昧な言葉を一言で説明できると、頭がよく見られます
効果の非常に大きいコツなので、定義はきちんと説明できるようにしておきましょう
わかりやすい説明のコツ4:聞き手の知っていることを話す
聞き手がすでに知っていることと説明したいことをくっつけることを「アナロジー」といいます
アナロジーを使うと、聞き手の理解力が高まります
アナロジーを使うとなぜ理解度が高まるのかというと
わかったような気にさせることができる
からです
人は自分の知っていることや知りたいことにしか興味がありません
そのため、自分の知らないことや知りたくない情報は、初めから話を聞きません
自分の知っている話を聞くと
「ああ、あのことね」
と、納得してこちらの伝えようとしていることを勝手に理解したように気になります
話が全く噛み合っていないにもかかわらず、お互いが理解し合っているような会話をしている人見かけることがありますが
あれのことです
聞き手の知っていることや興味のあることを持ち出して、話し手の伝えたいことをくっつけることで、相手の理解度を高めることができます
また、難しくて伝わりにくことも理解したような気にさせることもできます
悪用は厳禁ですが、説明の難しいことや相手を煙に巻きたいときはアナロジーを使うことにより、うまく逃げることができます
わかりやすい説明のコツ5:語源を解説する
日常であまり使われない専門用語やカタカナ言葉を解説するときに便利なものが、語源解説です
その言葉の語源を解説することにより、相手に言葉の意味を理解させることができます
例えば
「モチベーション」という言葉は、「動いて」「移動する」というラテン語に由来しています。つまり、相手の心が動いて行動を始める=動機と同じ意味です
という風に、語源を解説した上で身近な言葉に置き換えることで、言葉の意味をわかりやすく解説することができます
専門用語やカタカナ言葉を理解させるためには、その言葉の語源を解説して相手の理解度を高めましょう
わかりやすい説明のコツ6:言及した内容へのリンク
以前に説明したことや学んだことを繋げて説明をすると、相手にわかったと思わせることができます
子供と違い、大人はこれまでの体験や経験、学んだことと繋げて学習しようとします
「これは何と似ているかな?」
と、無意識のうちに考えています
大人になると、新しいことを覚えるのが難しくなるのはこのためです
聞き手に説明するときに、うまく話が伝わるようにするためには
- 相手の知っている言葉で説明する
- 過去に説明したことと繋げて説明をする
ことで、聞き手に話の内容を理解させることができます
相手が知らないことを話すときも相手の知っていることと繋げて話をすることで理解してもらいやすくなります
子供に説明するように、1からくどくど説明すると嫌われます
注意しましょう
わかりやすい説明のコツ7:比較対象を定義する
比較対象は、商品の良し悪しを区別する以外にも説明にも利用することができます
YouTubeとTikTokは動画を配信するサービスという点では同じです。
しかし、TikTokが10~30秒ほどの短い動画を投稿するのに対し、YouTubeは2~3分ほどの短い動画から30分以上の長い動画も投稿することができます
長い動画の中に宣伝広告を入れたいのであれば、YouTubuの方が御社の施策に向いています
などのように、共通や反対のものを比較対象として示すことで、伝えいたいことを短く説明することができます
比較対象を使ってわかりやすく説明するときのコツは
「ここは同じですが、ここが違います」
という言い方にすることです
また、よく使用する比較対象としては、「年齢」があります
多くのサービスは年齢ごとにターゲットを定めているので、利用者の年代の違いによる行動変容を比較することで、こちらの意図を簡単に説明することができます
わかりやすい説明のコツ8:視覚に訴える
口頭での説明をさらによくするためには、視覚情報を増やすことが大切です
プレゼンにグラフや表、画像などを利用するのはそのためです
口頭での説明を図や表で補うことにより、周囲に共通した認識を植え付けることができます
また、表情やジェスチャーなども大切な視覚要素の一つです
- 説明している内容とジェスチャーがあっていない
- 説明の最中に、体が左右に動く
など、余計な情報が入ると聞き手はそちらに意識を向けてしまいます
説明をしているときに、自分がどういった動きをしているのか?
一度確かめてみましょう
相手からの見え方を意識することで、あなたの説明力はグッと上がります
- まとめ
説明上手になるための話し方のコツについて解説をしました
説明上手になるためには
- 例え話を使う
- ストーリー仕立てに話す
- 定義を説明する
- 聞き手の知っていることを話す
- 語源を解説する
- 言及した内容へのリンク
- 比較対象を定義する
- 視覚に訴える
などを意識すると難しいことや伝えたいことを短くわかりやすく伝えることができるようになります
一度に全てを行う必要はありません
何か一つでも意識して話すことにより、少しずつあなたの説明は良くなります
自分に合う方法をぜひ見つけてください