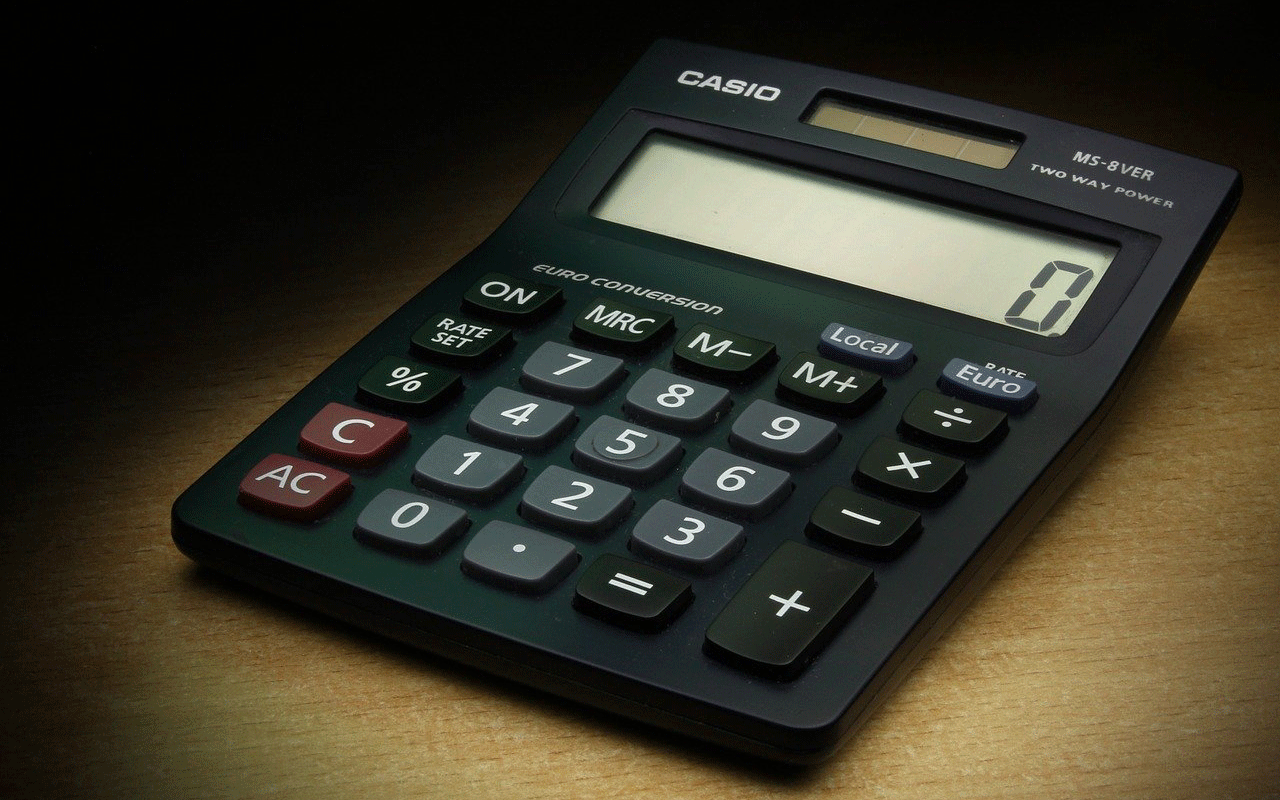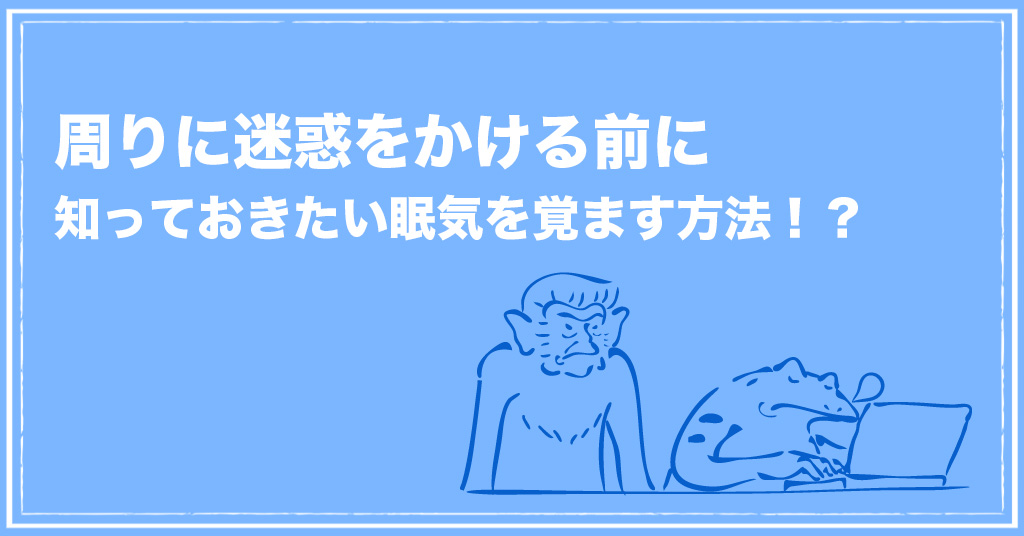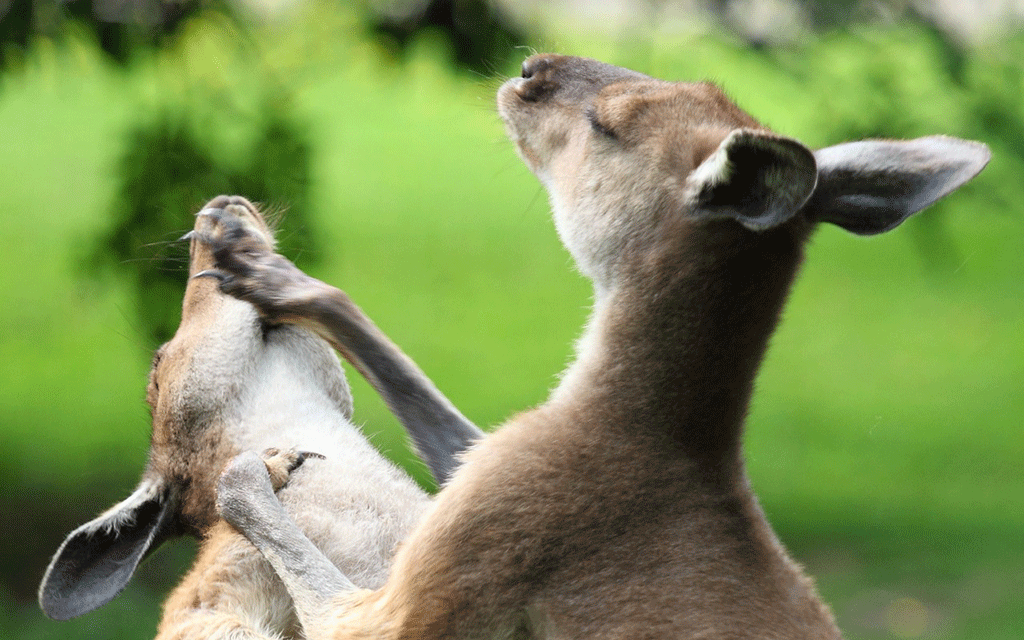ジョブ型雇用が広まると、今すぐ転職できるだけのスキルと実績がなければ、これまでのような報酬を得られなくなります。
ジョブ型雇用は、仕事を遂行するために必要なスキルを持った人と契約を交わし、その業務に対して報酬を支払う雇用形態です。
会社員がこれまでのような報酬を得るには、難易度の高く多くの成果を上げることが要求されるため、年功序列や終身雇用といった生活の安定を補償していた制度は崩壊します。
そのためジョブ型雇用の世界では、いつでも転職できるだけの自分になっておかないと、生き残ることが出来なくなります。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 実力がなければ、お金が稼げなくなるってこと?なんか怖い社会になりそうだね。
 ノリトモ
ノリトモ そうでもないさ。当たり前のことが当たり前のようにできればいいだけだから、そこまで心配する必要はない。
とはいえ、知らないことを知らないまま放置しておくと無駄な悩みを抱えことになり、対策もとれません。
大切なことは知識を蓄え、これからの自分の将来や働き方を考え、行動に移すことです。
この記事では、話題になりつつある「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」の違いとジョブ型雇用のメリット・デメリットについて解説をします。
 ノリトモ
ノリトモ 若くても十分に稼げるチャンスが来るぞ!
ジョブ型雇用とは?
ジョブ型雇用は、特定の職務を遂行できる人を採用する雇用のことで、年齢や社歴、学歴、意欲といったものではなく、スキルと実績が重視される雇用形態です。
これまでの日本の会社では、メンバーシップ型雇用を採用してきた企業が多く、社歴の差が仕事の範囲に影響を及ぼすため、長く会社に勤めることのできる社員を重要視してきました。
しかし、新型コロナウイルスの蔓延によりテレワークやリモートワークが急速に普及し、会社員の低生産性や人手不足、ダイバーシティなど様々な問題が浮き彫りとなりました。
そこでこれらの社会問題を一挙解決すべく、経団連の偉い人たちが「欧米で主流のジョブ型雇用にすべきでは?」という意見に乗っかり、ジョブ型雇用を推進する流れができました。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 欧米ではジョブ型の働き方が主流なんだね。
 ノリトモ
ノリトモ そうだ。米国の労働者の約6割がフリーランスだと言われている。
そのため巨大ハイテク企業の集まる米国のシリコンバレーに終身雇用で給与や生活が保障されている日本の会社員が研修に行って特に何の成果も残せないのは、ジョブ型雇用のフリーランスに囲まれているためとも言われています。
メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の違い
メンバーシップ型雇用
メンバーシップ型雇用は、従来の採用基準で雇用された雇用形態のことで、新卒を総合職として一括採用する雇用のことです。
メンバーシップ型雇用の特徴は、年功序列・終身雇用・転勤や異動もあるという昔から馴染みの深い雇用形態です。
会社に正社員として雇われる従業員は、「この会社のメンバーとして一生懸命がんばります!」と面接時に意気込みを見せるポテンシャルを買われて採用に至ります。
一方、会社側も「ずっと面倒を見るから、こちらが指定した場所で言われた通りの内容の仕事をしてね」と社員の生活の安定を約束する代わりに、従業員に居場所を与えます。
そのため「就職」ではなく「就社」という考えを持つことが大切で、従業員の評価は会社への忠誠度や勤続年数となり、転職することが不利となる構造となっています。
ジョブ型雇用
ジョブ型雇用の業務形態は、外資系企業などで見かけるジョブディスクリプション(職務記述書)に沿って、仕事内容・責任範囲・必要スキル・労働条件・期待目標・上司部下などが明確に定義された形のもと就業します。
ジョブ型雇用で雇われた従業員は、「約束通りの仕事をします」と契約の範囲内で企業に求め荒れた成果達成のために仕事をします。
会社側も「約束通りの仕事をしてくれたら、約束通りの待遇と報酬を提供します」とこちらも契約の範囲の中で契約通りの報酬を支払います。
従業員は求められた成果を返す限り、スキルを前提に報酬を受け取ることができるメリットがあり、会社と従業員の間で対等な関係を構築することが出来ます。
ジョブ型雇用のメリット
以降は、従業員の観点から見たジョブ型雇用のメリットを紹介します。
メリット1.仕事を選べる
メンバーシップ型の雇用では、新卒の総合職採用が一般的で専門職の採用は少数派でしたが、ジョブ型雇用になると自分の仕事内容を自分で選べるようになります。
営業、経理、総務、マーケティングなど内容の違う仕事内容を自分で選んで、今後のキャリアを考えて、自分に合った働き方を見つけていくことになります。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 会社が仕事内容を用意するんじゃなくて、自分で選んでキャリアを作っていかないといけないということ?
 ノリトモ
ノリトモ そうだ。総合職っていうざっくりした採用はなくなるし、人材を育てるために、3〜5年で部署を異動する「ジョブローテーション」なんて悠長なことをしていられなくなる。
ジョブ型雇用になれば、自分の望む職種で働けて、会社の都合による部署異動や職種変更に悩まされることがなくなります。
専門スキルも磨きやすくなり、転職もしやすくなるため、就職してから定年まで一つの会社に就業をし続ける必要もなくなります。
メリット2.給料が増える
仕事を頑張っても頑張らなくても、給料に差のないメンバーシップ型雇用と異なり、ジョブ型雇用では仕事が増えれば増えるほど給料も増えます。
ジョブ型雇用がその名の通り、ジョブ=仕事に対して報酬を支払う雇用形態であるため、仕事の範囲が広くなり、責任が重くなれば、その分の報酬が変わってきます。
反対に、働いても働かなくても給料がもらえるのなら、「働かなくてもいいんじゃない?」と高をくくって働かない「働かないおじさん」は給与が全くもらえなくなります。
 ノリトモ
ノリトモ 働かないおじさんは雇用されないし、従業員を監視・管理しているだけの「なんちゃって管理職」も必要ない。
ジョブ型雇用では、自らスキルを磨き、たくさんの仕事をして、より難易度の高い仕事に挑戦し、成果を上げることができれば、もらえる給料も増えていきます。
優秀な若い従業員にも平等にチャンスが巡ってきます。
メリット3.忠誠心よりスキルを評価
ジョブ型雇用は仕事の成果で評価するため、一番重要な評価指標は「仕事をこなすスキル」をもっていることです。
そのため、これまでのように周囲の目を気にして無駄に残業したり、仕事後に飲みに付き合うなどの会社への忠誠心を示す必要性が下がります。
仕事を増やすチャンスを作るための営業活動としての付き合いは必要かもしれませんが、頑張っている感を出すよりスキルの有無が重要です。
そして成果を出している限り、ワークライフバランスや副業、転職を視野に入れた自己投資活動などスキルを磨くことを前提とした多様性が認められる社会になります。
メリット4.転職の自由化
ジョブ型雇用が広がれば、雇用の流動化が進み、転職市場はこれまで以上に活性化することになります。
自らのスキルが売り物になるため、従業員の多くが新しいスキルと実績をつくるため積極的に転職や働く場所を求めて活動をするからです。
これまでの企業は、なにか新しい事業を始めるときには社内から人事異動をして人材を育てる活動をしていましたが、これからはすでにスキルと実績のある人を中途採用して仕事の成果を期待するようになります。
そのため、会社員はこれまで以上に自分にできる仕事の内容を把握する必要があり、そのスキルを高く買ってくれる会社を求めて転職に前向きになっていきます。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん ジョブ型ってすごいね。仕事へのやる気が湧いてくるね。
 ノリトモ
ノリトモ そうか。では、これからジョブ型のデメリットも紹介しよう。ジョブ型雇用になることで、「得をする人」もいれば「損をする人もいる」。自分がどちらに属するか知ることが大切だ。
ジョブ型雇用のデメリット
デメリット1.給与が補償されない
ジョブ型の雇用では、これまでのような制度が見直される可能性があります。
年功序列
家族手当
営業手当
皆勤手当
住宅手当
退職金
終身雇用を想定して作られたこういった制度が見直され、成果に応じた給与になるのがジョブ型です。
いまのあなたの年齢や住んでいる場所、不要している家族の数など仕事の成果に関係のない要素は徹底的に排除されます。
成果に応じて給料は上がりますが、成果を出せなければ給料は下がるし、成果に関係のないて後なども排除される可能性があります。
会社に来て座っているだけでもらえていた給料や手当がもらえなくなります。
デメリット2.事実上の非正規化
ジョブ型で人を雇用するということは、仕事内容に基づいて報酬を支払うことです。
つまり、仕事がなければ報酬は支払われませんし、雇われることもありません。
これまでの正社員は、会社から理由のない減給や降格、解雇がされないように法律で守られていました、ジョブ型雇用になると雇用の流動性が認められるようになるため、これらのことが身近になります。
つまり、安定した正社員という身分が失われ、解雇されたくなければ、自らスキルを広げ、人脈を深めたりする工夫が余儀なくされます。
会社に来て、ただ座ってネットサーフィンをしていても怒られませんが、そうした人はすぐに解雇されるようになります。
デメリット3.会社での学びがなくなる
ジョブ型雇用になると、仕事をしながらスキルを磨くということがそもそもなくなります。
スキルを元に雇用されるためです。
そのため、メンバーシップ型雇用では廃止部門の従業員を他部門に異動させたり、新しい部門に再配置されたりして、会社が社員の人材育成を重視していましたが、ジョブ型雇用では廃止部門の従業員は解雇されます。
新卒採用にしてもポテンシャル採用のようなこともなくなり、学歴ではなくスキルや実績ベースでの採用が基本となります。
会社は学ぶところではなく、学んできた知識や経験を発揮するための場所となり、そのためにいつでも転職できるだけのスキルと実績を準備をしておくことが大切です。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん なんかもうイス取りゲームみたいだね。。。
 ノリトモ
ノリトモ そうだな。イスの数が多いほど有利になる社会がジョブ型雇用の世界だ。
ジョブ型雇用との向き合い方
ジョブ型雇用が広まると、会社と従業員に対する姿勢が変わり、その関係性も変わります。
これまでのように、「ずっと面倒を見るから、こちらの言うことを聞いて、言われた通りのことをしてね」というような親子関係ではなく、「契約上の関係だから、自分のことは自分で考えてね」というドライな関係に変化していきます。
従属的な契約やから対等な契約に変化することで、会社が従業員に求めるものが変わり、それに対して従業員が会社に提供するものも変わります。
会社員の側から見れば、メンバーシップ型で何もしなくても利益を享受できていた人はこれからの社会の変容に恐れ慄いているかもしれませんが、働いても評価をされなかった人にとってはチャンス到来ともいえます。
どちらにしても働き方の自由度が増えると同時に、仕事に対する責任は重くなります。
ワークライフバランスを考えて仕事をセーブしながら働くのか、スキルと実績を重ねることを重視してひたすらに働くことを考えて、時間を犠牲にして給料を増やすのか。
ジョブ型雇用が一般化されれば、今の会社にも止まれない世界がやってくる可能性もあります。
それまでの間に自分のベストな働き方を考えて、どちらでも働けるように準備しておきましょう。
まとめ
- ジョブ型雇用は、スキルと実績が重要視される
- ジョブ型雇用は、欧米では一般的
- 給与が増え、給料が増える可能性がある
- 会社や上司への忠誠心は関係なくなる
- 正社員の非正規化であるため、給与や身分は補償されない
- 会社は学びの場ではなく、実践する場となる
- 常に転職できるだけのスキルと実績を用意しておく必要がある