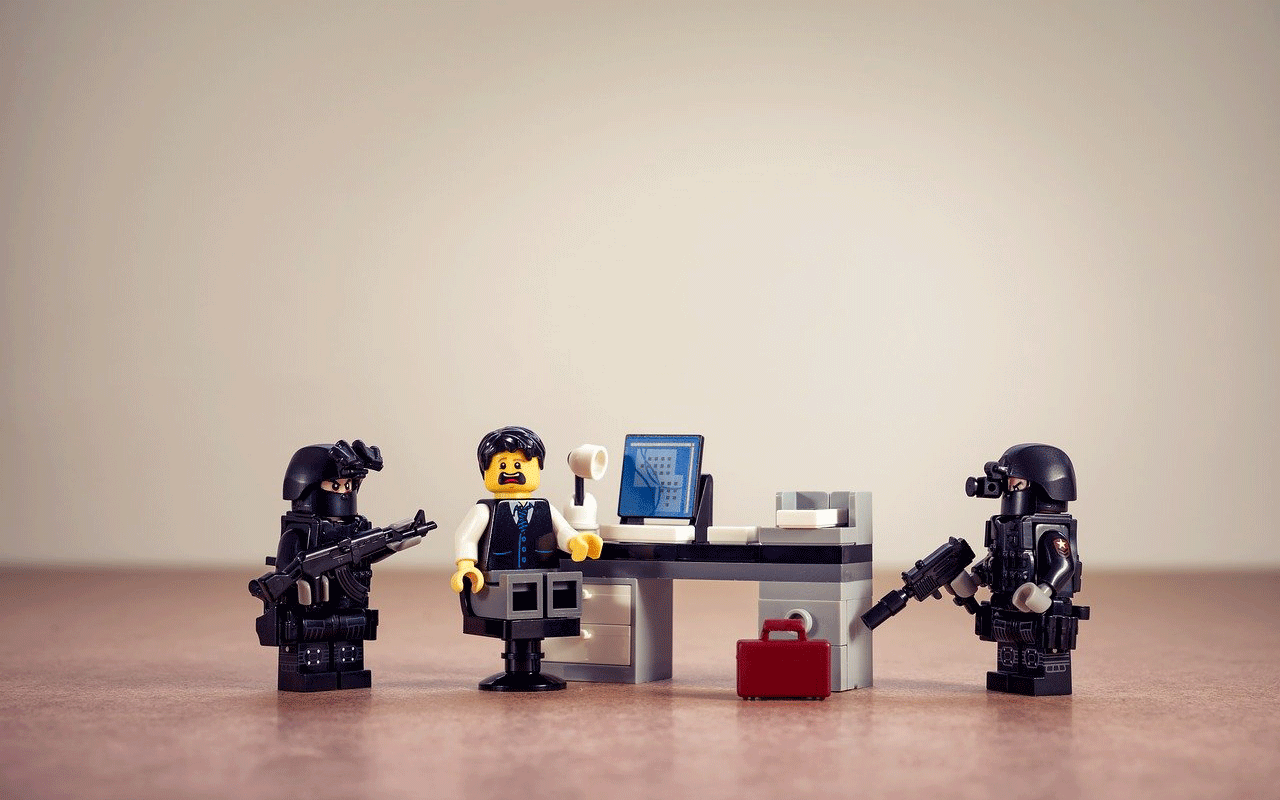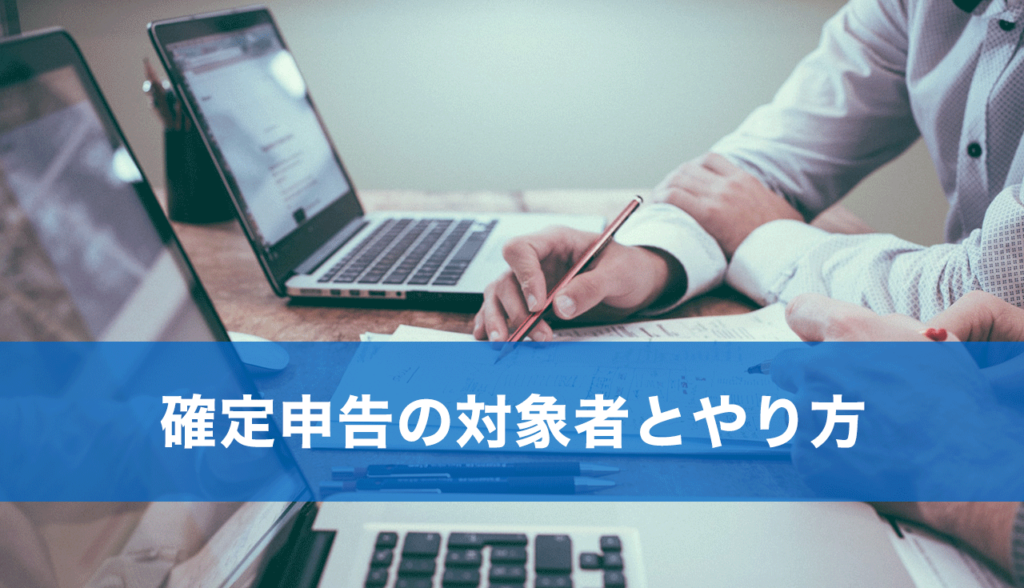
副業を始める人が増える中、今年初めて確定申告をする方や毎年申告をしているけれど、ついついその期間を忘れてしまう。そんな人も多いはず。
確定申告は、原則として2月16日から3月15日の1ヶ月の間に行う必要があります。
ただし、該当日が土日祝日の場合は繰り下がることになるため、開始日の2月16日が2月17日や2月18日に変更することがあったり、終了日の3月15日が3月16日以降になったりすることもあるので、ご注意ください。
そんな確定申告ですが、一体どんな人が対象者なのか?自分は対象者なのか、そうではないのか?いま一つわからない部分があります。
今回は、個人事業主や副業をしている会社員をはじめ、どういった方が確定申告の対象者となるのか。
また、確定申告のやり方について解説していきます。
確定申告はいつまでに!?
大事なことなので、改めて確定申告の期間とその対象期間を明記しておきます。
確定申告は、1年間の所得に関する情報を申告し納税する制度です。
その対象となる期間の1月1日から12月31日までを期限とし、原則として2月16日から3月15日までに申告を行う必要があります。
申告を怠った、忘れてしまった場合は!?
期日までに申告をしなかった、または忘れてしまった場合は、申告によって納める税金に加え、無申告加算税もしくは延滞税という税がプラスして課されます。
国税庁のホームページでは、課税に対する対応を以下のように定義をしています。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
国税庁:No.2024 確定申告を忘れたとき
確定申告の対象者は!?
確定申告といえば、フリーランスや個人事業主が、その対象者というイメージにあります。
しかし、条件によっては給与収入の会社員やパート収入の主婦の方もその対象となることがあります。
確定申告の対象者
- 給与収入だけで2,000万円を超えている人
- 副業の所得が20万円を超えている人
- 年末調整を行なっていない人
- 年度の途中で無職となった人
- 転職して、退職した会社の源泉徴収票を転職先に提出していない人
- 2つ以上の会社から給与を受け、まとめて年末調整をおこなってもらえない人
給与収入だけで2,000万円を超えている人
給与所得が2,000万円を超えると、年末調整が行われません。
そのため、1カ所から2,000万円を超える給与を受けている人は必ず確定申告を行わなけければいけません。
副業の所得が20万円を超えている人
最近では、会社員だけど副業で空いた時間に副業をしている人が増えてきました。
こうした人の中で、年間の所得が20万円を超える人は確定申告が必要となってきます。
なお、原則として収入から必要経費を引いた金額が20万円を超える人が対象となるため、必要経費を引いた額が20万円を超えなければ、確定申告は必要ありません。
年末調整を行なっていない人
バイトやパートは年末調整対象外という会社もあります。
こうした会社でバイトやパートをしているフリーターやパートの主婦の方は、年明けにもらう源泉徴収を元に確定申告を行う必要があります。
年度の途中で無職となった人
年度の途中で理由があり、会社を辞めないといけない場合もあります。
こうした方で以前の会社で年末調整をしていない方は、確定申告が必要です。
※年末調整を行なっている人は必要ありません。
転職後、退職した会社の源泉徴収票を転職先に提出していない人
転職した際に、転職先の会社から源泉徴収票の提出を求められることがあります。
これは退職した会社と転職先の会社での年末調整を同時に行なってもらうためです。
仮に、源泉徴収票を紛失したり、もらっていない場合は、退職した会社から改めて源泉徴収票をもらう必要があります。
退職した会社と転職先の源泉徴収票を元に、転職した会社もしくは自分で確定申告を行います。
2つ以上の会社から給与を受け、まとめて年末調整をおこなってもらえない人
確定申告を行えるのは、原則1社までです。
そのため2つ以上の会社から給与所得を受けている人は、年末調整が必要です。
確定申告のやり方
1.必要な書類を準備する
事業所得の他に給与所得がある場合は、源泉徴収書などを準備しておきます。
また、他に用意する書類と以下のようなものが考えられます。
- 医療費の領収書
- 生命保険の控除証明書
- 寄附金(ふるさと納税など)の受領証など
申告書を準備する
確定申告には「A」「B」2種類の申告書があります。
事業所得がある場合は、「B」を使用します。
※繰り越された損失額を本年分から差し引くことができます。
付表と計算書等を準備する
申告内容に応じて付表、計算書等を準備します。
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
- 給与所得者の特定支出に関する明細書
- 特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 政党等寄附金特別控除額の計算明細書
- 認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
- 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
- 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
- 外国税額控除に関する明細書
- 居住形態等に関する確認書
- 所得の内訳書
- 医療費の明細書 など
確定申告書を作成する
申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成することができます。
手引きに従って、申告書を記入します。
添付、提示する書類を確認する
申告書の他に、源泉徴収票や生命保険の控除証明書などを添付、または提示する必要があります。
書類を添付する場合は、添付書類台紙などに貼り付け申告書と一緒に提出します。
確定申告書を提出する
申告書は以下の方法のいずれかで提出できます。
- 郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する
- 住所地等の所轄税務署の受付に持参
- e-Taxで申告する
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、e-Taxにより24時間送信できます。
納税する、または還付を受ける
納税をする場合
- 振替納税を利用する
- 現金で納付する
- e-Taxで納付する
還付を受ける場合
申告書に記入した金融機関の預貯金口座に還付金が振り込まれます。
まとめ
確定申告の対象者とそのやり方について、解説をしました。
意外とその範囲は広く、ともすれば自分が対象者であることにも気が付かないこともあります。
確定申告を怠ったり、忘れた場合は、「無申告加算税」や「延滞税」など追加で税金を支払わないといけません。
また、その行為が悪質であると判断された場合は、刑事事件に発展する恐れもあります。
申告に慣れていない方は、専門家に相談したり、ウェブサイトの有料サービスなども利用されることをおすすめします。
白色や青色申告など自身の状況に合わせた申告に対応しており、カンタンに確定申告書を作成することができます。
時間のない方もそうでない方も、なるべく余裕を持って申告を行いましょう。