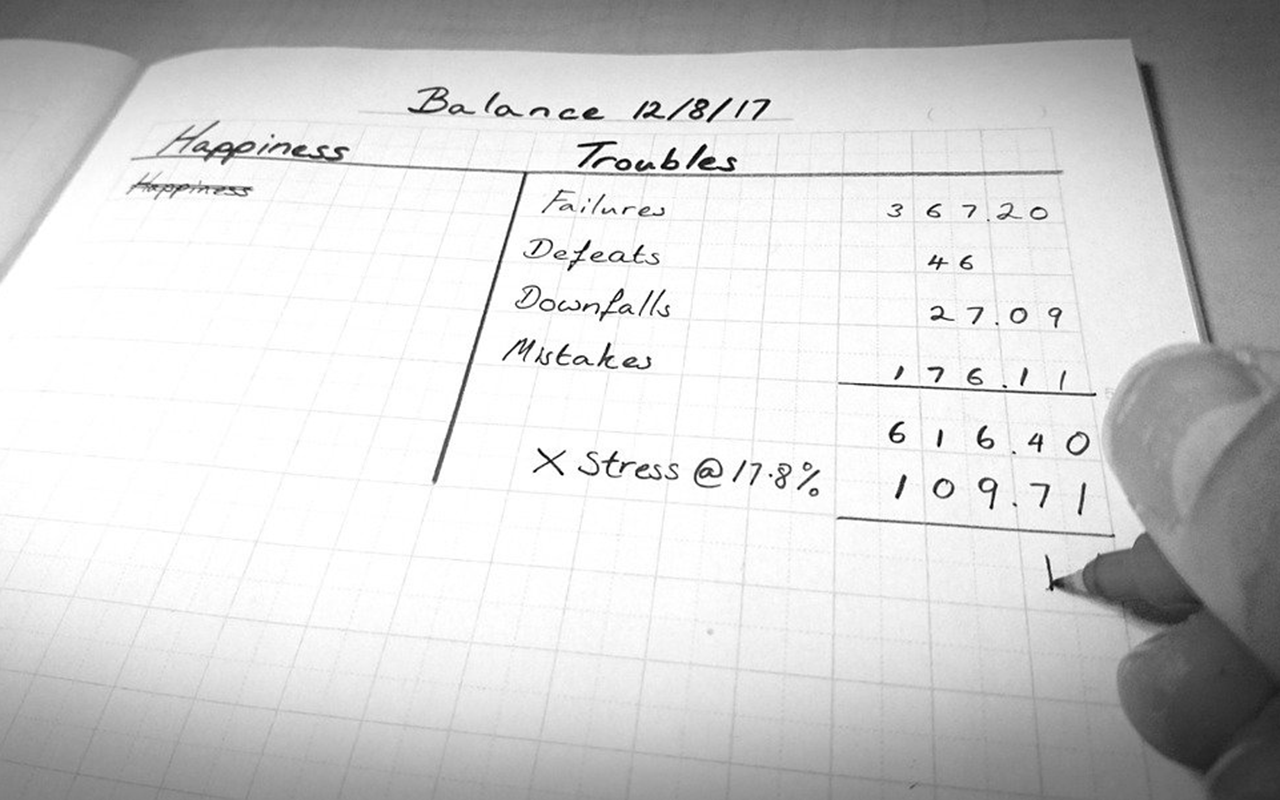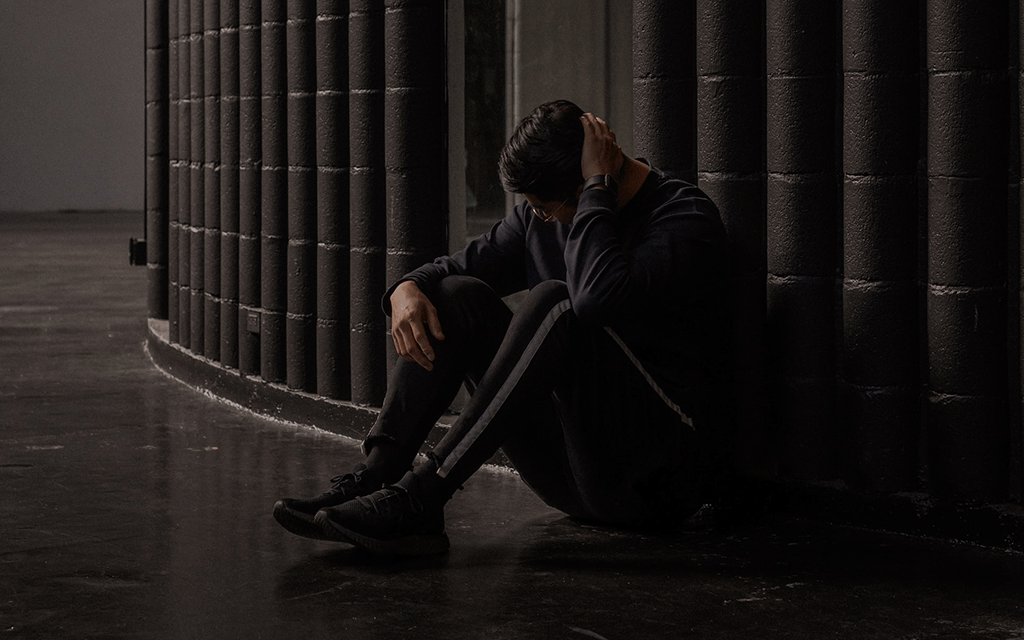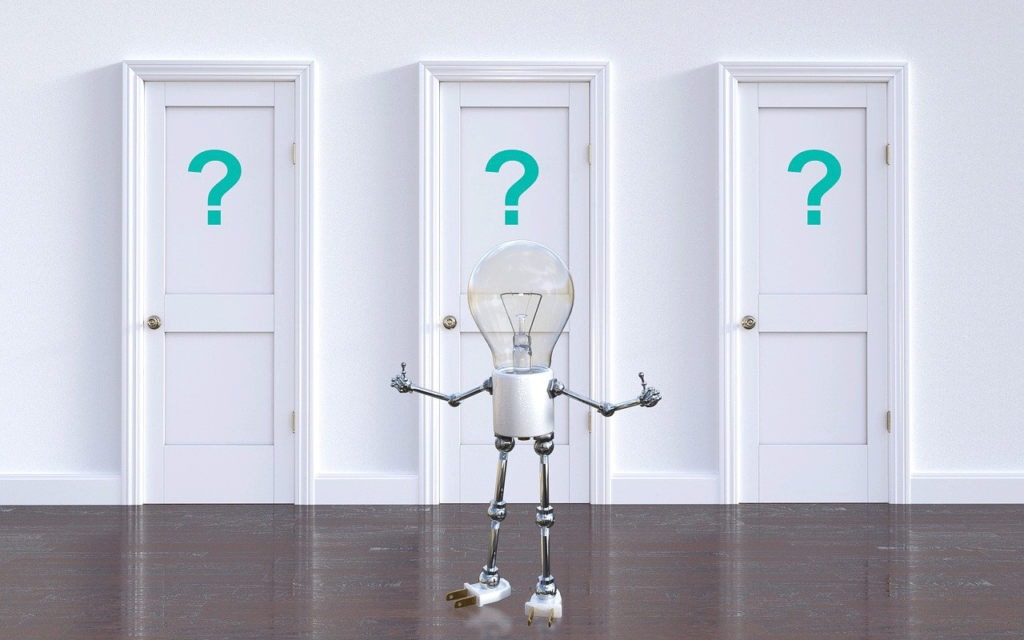
こんな人におすすめ記事
- 簿記3級試験の合格を目指している
- 仮払金と仮受金の仕訳を知りたい
- 立替金との違いが分からない
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 以前出張したとき、出張費用をあらかじめもらって出張したんですけど、精算するときに何にいくら使ったのか忘れちゃってすごく焦りました。
 ノリトモ
ノリトモ 電車やタクシー代とかの交通費は、メモしておかないと忘れるよね。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん アフィリエイトとかの広告収入の精算もうっかり忘れることがあって、経理の人には迷惑をかけてるんだろうなって反省してます。
 ノリトモ
ノリトモ 簿記会計ではそうした使途不明金の処理もきちんと仕訳する必要があるから注意しようね。
仮払金・仮受金とは?
何のお金なの、これ?
会社の経理を担当していると、よくわからない不気味なお金が口座から出入りします。
この中身のよく分からないお金の仕訳に用いる勘定科目が「仮払金」と「仮受金」です。
仮払金は、使用使途の不明、もしくは金額が未確定の場合に一時的に支払われるお金を指します。
仮払金は貸借対照表では、「資産」に分類される勘定科目で、一般的には「流動資産」に表示されます。
「仮に支払うお金なのに、なぜ資産にするの?」と思うかもしれませんが、仮払金はまだ使い道の決まっていないお金として一時的に貸し付けたというイメージです。
そのため貸付金と同じように、資産として分類します。
仮払金とは反対に、使用用途の不明なお金を一時的に受け取るお金を仮受金といいます。
仮受金の貸借対照表での表示は、「負債」となります。
仮受金が負債になる理由は、「未来の勘定科目を振り替える義務」があるためです。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 支払うものは負債だと思いがちですが、逆なんですね。
仮払金の仕訳
例題1-1.
出張をする従業員に、現金10万円を渡した
(借)仮払金100,000(貸)現金100,000
例題1-2.
帰社した従業員が、出張経費としてかかった諸費用のタクシー代1万円と電車代5万円を申告し、残金を返金した
(借)現金40,000(貸)仮払金100,000
(借)旅費交通費60,000
例題2-1.
業務用に使用しているICカードに現金1万円をチャージした
なお、チャージしたときの勘定科目には「仮払金」を使用する
(借)仮払金10,000(貸)現金10,000
例題2-2.
従業員がICカードを使って電車代を五千円支払った
(借)旅費交通費5,000(貸)仮払金5,000
 まい
まい 近年の簿記3級試験では、ICカードなどチャージできる電子マネーからも出題されるよ。
仮受金の仕訳
例題1-1.
代金不明の1万円が当座預金に入金された
(借)当座預金10,000(貸)仮受金10,000
例題1-2.
売掛金の回収であることが、後日営業への聞き込みにより判明した
(借)仮受金10,000(貸)売掛金10,000
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 請求処理をし忘れたときに、たまに経理から確認のメールが飛んできますよね。
立替金との違いについて
仮払金と間違えて仕訳されるものに、「立替金」という勘定科目があります。
仮払いと立て替え・・・似たような言葉でややこしいですが、簿記会計では異なる勘定科目として定義されています。
仮払金と立替金の一番違いは、「費用を誰が負担するのか?」という点です。
仮払金の場合は、いまは使う用途がわかっていないお金を従業員に貸し付けるイメージです。
そのため、最終的な費用負担は会社になります。
一方、立替金の場合は、従業員が負担すべき費用を会社が一時的に立て替えて支払いを行います。
この場合の最終的な費用負担は従業員になります。
仮払金が「負債」に分類される勘定科目なのに対し、立替金は「将来返してもらえるお金」として「資産」に分類されます。
立替金の仕訳
例題1-1.
従業員が負担する生命保険料1万円を現金で支払った
(借)立替金10,000(貸)現金10,000
例題1-2.
立て替えた金額は、その月の給与分から差し引いて残額を給与として支給した
従業員の給与は35万円で、所得税9,800円、住民税6,300円、社会保険料43,000円とする
(借)給与350,000(貸)預り金59,100
(貸)立替金10,000
(貸)現金280,900
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 仮払金と立替金は言葉は似ていますけど、処理を見るとイメージが全然違いますね。
まとめ
仕事をしているとたまにお世話になっている仮払金と仮受金について解説をしました。
仮払金はいまのところ使う用途は不明のお金ですが、将来支払う予定のお金であるため「負債」として仕訳します。
仮受金の場合は、入金先などが不明なお金を仮に引き受ける「資産」として仕訳します。
立替金などと混同しがちの仮払金は、最終的に支払いを負担する先の違う勘定科目であるため、その仕訳は全く反対の処理をします。
それぞれの言葉と内容の違いを理解して、仕訳できるように慣れていきましょう。