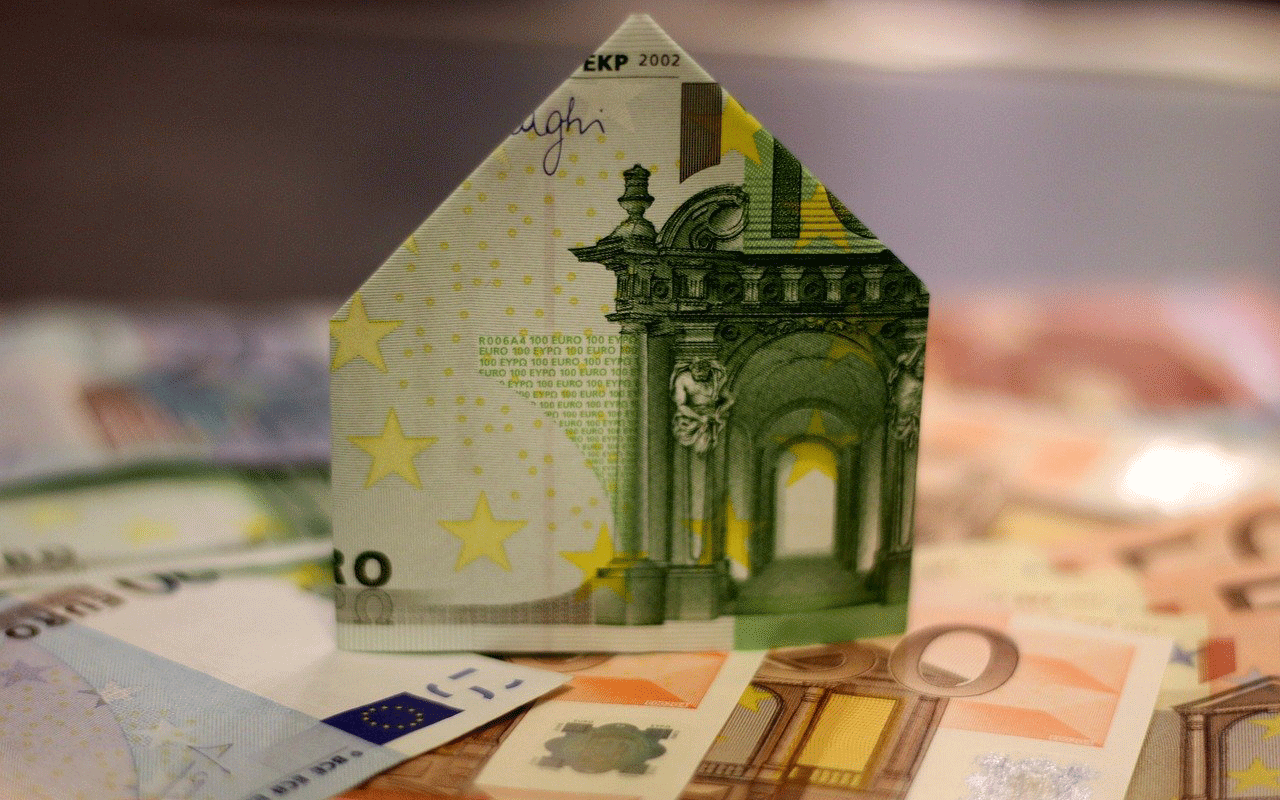アシのMちゃん
アシのMちゃん 会議の司会進行が苦手です。どうすれば上手く場を仕切れますか_
こんな人のための記事です。
仕事をする上で、会議やミーティングは必要不可欠です。
しかし、会社の会議で複雑な議論や合意が必要な会議は多くありません。
むしろ、会議を成立させること自体が難しいと感じる会議もあります。
そういった意味のない会議を取り仕切ることになったとき、意味のない会議を開いた責任や進行が上手くできないことに悩んでいる方もいるかと思います。
結論を先に言うと、「会議はその目的とまとめを冒頭と終了で話す」ことで、周囲に「会議に意味があった」と認識させることができます。
この記事では、会議の進行が苦手な人や議論の必要のない会議で進行役を任されたときに、どうすれば会議を上手く進めることができるのか?について解説をします。
開催が必要な会議と不必要な会議の違い
そもそも会議には、開催が必要な会議と不必要な会議の2種類あります。
開催が必要な会議とは?
メールや担当者間同士のコミュニケーションだけでは決めづらい、複雑な議論や合意が必要な場合は、関係者を集めて会議をする必要があります。
開催不要な会議とは?
情報共有や進捗確認だけで済む会議、目的なくなんとなく開かれる会議は、そもそも必要ありません。
しかし大半の企業の会議は、担当者や上司への報告・連絡で済むものか、「とりあえず関係者を集めて話をしたい」などの理由で開催される-目的意識の薄い会議ばかりです。
そういった会議への参加は、断るか途中退場すれば大丈夫ですが、進行役を任された場合はそういうわけにもいきません。
以下では、良い会議や悪い会議に関わらず、会議の進行役をするときにこれさえ押さえておけば「会議の体裁を保つことができる」という方法について、解説を続けます。
良い会議の体裁を保つ方法
参加者が参加してよかったと仕事をした感じのする会議とはどういったのものなのか?
答えは、会議の目的が達成できたかどうかです。
そのためには、会議の目的をはっきりさせ、参加者をそのゴールに導く必要があります。
これが会議の司会進行の役割です。
会議を盛り上げたり、予定時間まで議論をさせることが目的ではありません。
では、目的意識をもってゴールに導くためにはどのように会議を進行するのか?
以下に、会議を進める手順とそのポイントについてまとめました。
会議を進める手順とポイント
STEP1.議題(目的)と一緒にゴール(終了条件)を確認する
会議の冒頭では、その会議の議題や議事(アジェンダ)などの目的確認をよく行います。
しかし議題や議事の確認だけでは、話が途中で脱線したり、そもそも何のために話し合いをしているのかわからなくなったりすることもあります。
そうした状況にならないためには、「いつ・誰が・何のために・何をするのか決めたい」など会議の狙いやゴールを冒頭で示す必要があります。
情報共有や進捗報告だけの会議であれば、そのことを明確にして、スパッと終わらせてしまうのも一つの手です。
しかし、そう言った場合は、あらかじめ余った時間で議論する議題を用意しておくか、終わらせるときに周囲に確認するなどの配慮も必要です。
STEP2.余った時間を活用する
会議が進まない理由は、話がそれてしまっていたり、余りそうな時間を無駄に引き伸ばしているときです。
そうした場合の解決方法は、「余った時間で議論をする」ことを明確にします。
時間が余ることを明示しておくことで、議題にそれた話を棚上げすることができ、時間が余っても罪悪感がわかないため、スムーズに議事を進行することができます。
仮に、時間が余らなかった場合は、異なる議題で会議を後日開催するか、関係者にヒアリングした上で進めさせてくださいと一旦時間を開ければ大丈夫です。
STEP3.会議の終盤に決まったことを再確認する
会議の終盤で、決まったことを再確認することで後日の認識違いを防ぐことができます。
また、会議の決定事項は会議をした成果であるため、それを明確にすることで参加者の達成感を誘発する効果もあります。
発展性のない会議でも情報共有ができたことを発表しさえすれば、参加者の満足感を煽ることもできます。
会議を成立させる5つのコツ
会議の進行役を務めるとさまざまな障害にぶつかります。
そうした場合の対処法を5つご紹介します。
ホワイトボートを使う
ホワイトボードを使うと会議がそれっぽくなります。
議論した内容を逐次書き込むのは大変なので、メモ書き程度で活用ください。
ホワイトボードに必ず書いておく方がよいのは、議題(目的)とゴール(終了条件)のみです。
そうすることで、会議の参加者は議論の脇道に逸れずに、議論を展開してくれます。
意見をまとめる
会議の進行で一番むずかしいのが、議論をまとめることです。
議事ごとに意見をまとめつつ、担当者と認識を合わせながら議論を進めていきましょう。
その際、こちらの認識が間違っていても大丈夫です。
都度、認識を訂正してもらいながら進めるぐらいがちょうど良いと思います。
今いるところを確認する
議論が白熱してくると何について話をしているのかわからなくなるときがあります。
そうした場合は進行役が、今話しているところを参加者に呼びかける必要があります。
ときには、参加者の中で迷子になっている人がいないかどうか目を配ることも大切です。
名前を呼ぶ
人の名前はインパクトがあるので、誰に意見を聞いているのか、これは誰の意見なのかなど、だれをの部分を明確にすることで会議の進行を掌握できます。
会議の話が膨らんだり、抑えが効かない状態になったときなどは名前を呼んで会議を抑圧しましょう。
困ったときは上司に話を振る
進行をしているときに上手く話をまとめられなかったり、意見を言えないときがあります。
そうした場合は、上司を上手く使いましょう。
会議前から上司と認識を合わせをしていれば、その上司が上手くフォローをしてくれます。
仮に上手くフォローできなかったとしても落ち込むのは上司の方なので、困ったときには上司に話を振ってその時間を使って冷静になり、自分なりの回答を用意しましょう。
まとめ
会議の進行が苦手な人や議論の必要のない会議で進行役を任されたときに会議の体裁を整える方法について解説をしました。
会社では必要のない会議がよく開催されます。
参加するだけなら、黙って座っていればいいですが、進行役になると会議を意味のあるものにしなければいけません。
そうした場合も会議の目的やゴールを明確にしてから、会議を始めることでスムーズに会議を進めることができます。
また、会議の終盤では決まった内容を反芻することで、会議の参加者に達成感を感じてもらうことができます。
会議に限らず、大切なのは始まりと終わりをきちんと意識することです。
困ったときは他人に話を振って誤魔化しましょう。
参考になれば幸いです。