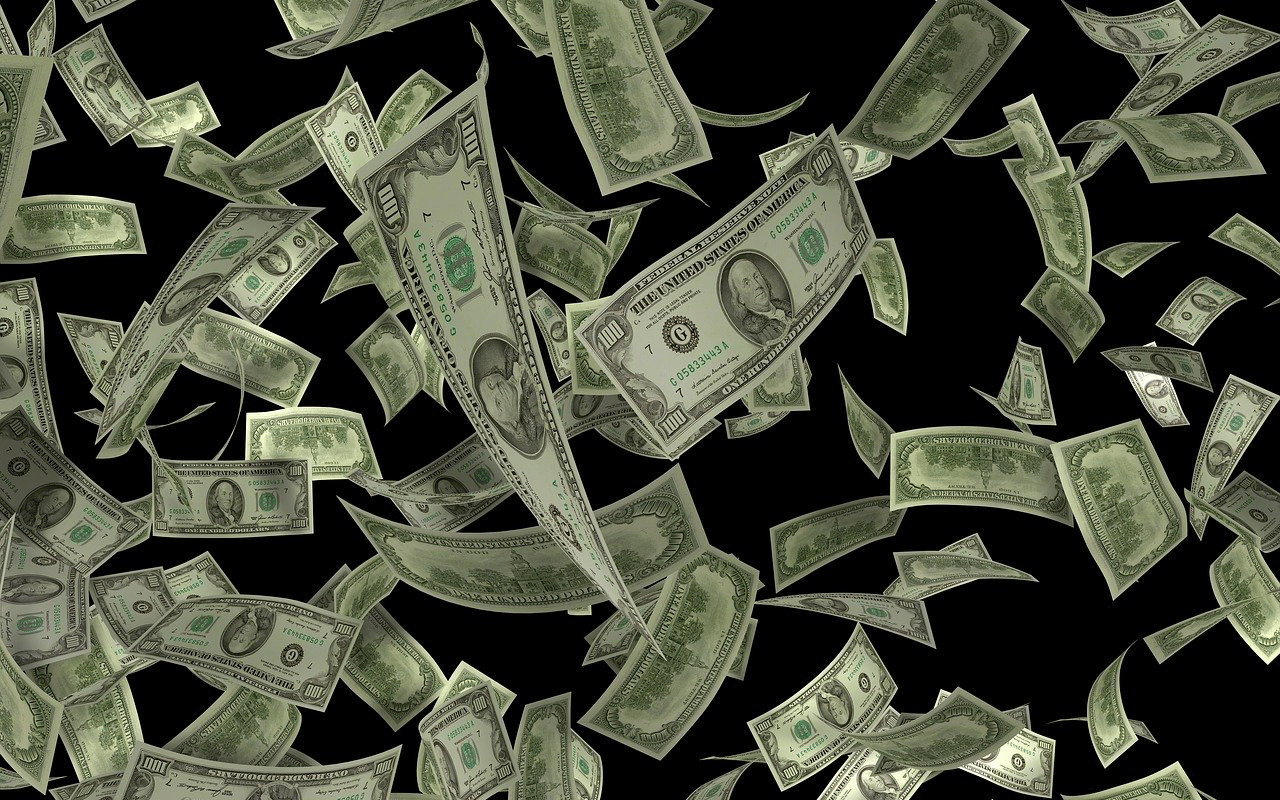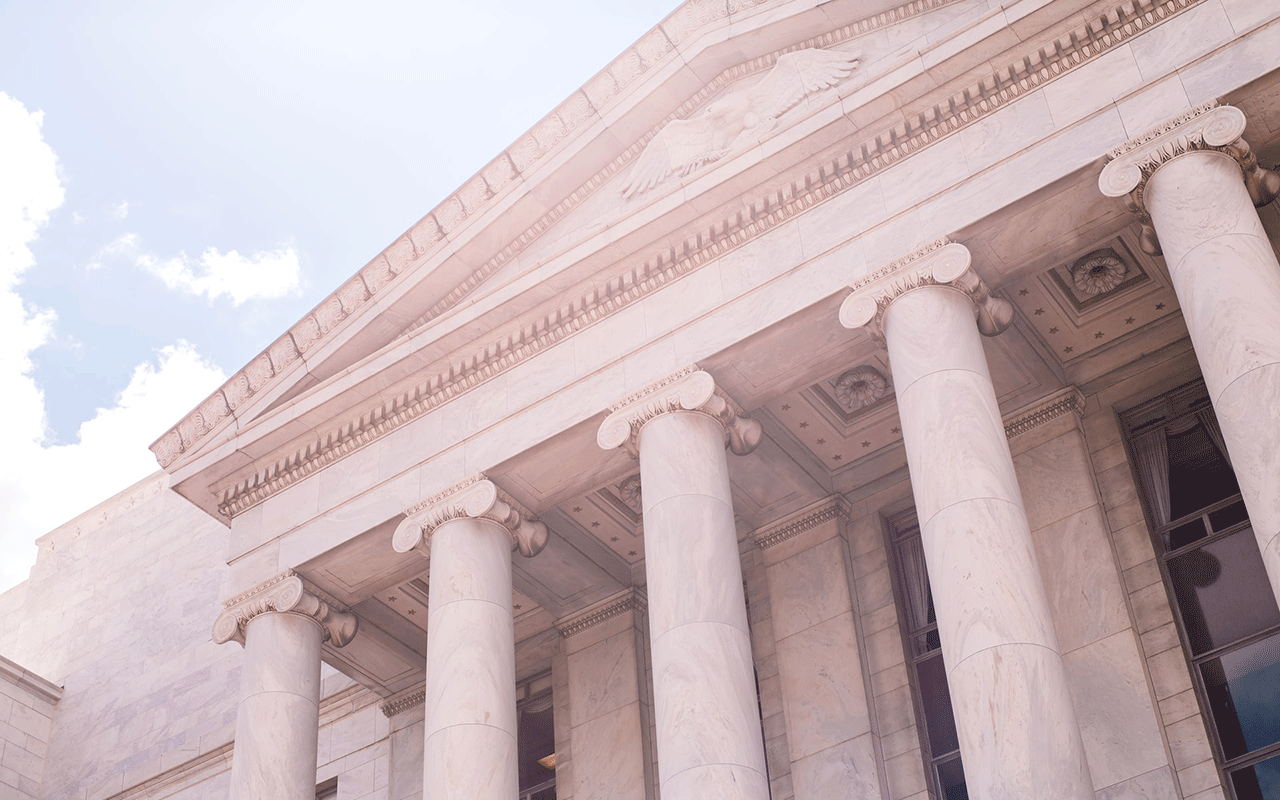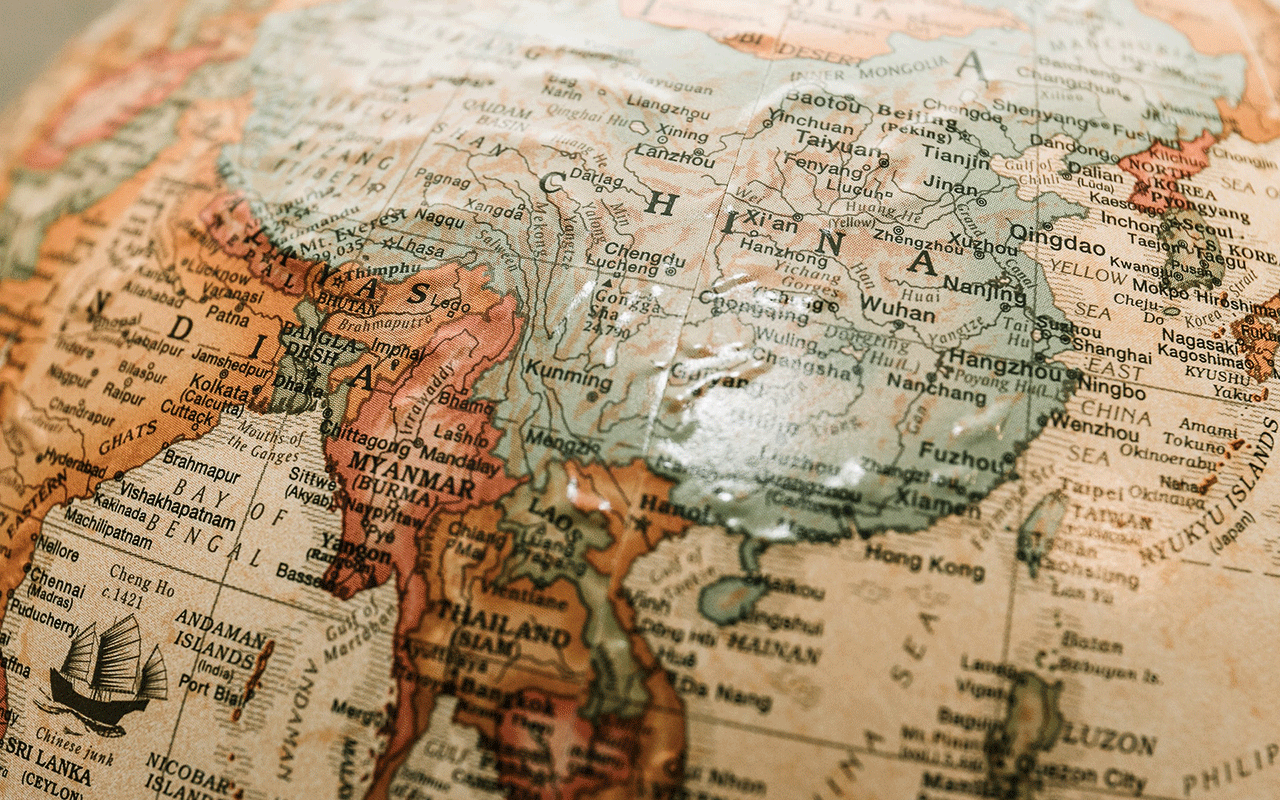小額から投資を始められるNISAについて、こんな悩みを解決する記事を作成しました。
この記事で解決できる悩み
- それぞれのNISAの変更点は?
- すでに一般NISAを使っている人はどうなるの?
- 結局、新NISAとつみたてNISAはどっちがいいの?
2024年からNISA制度が変更!?
税制改正によって、2023年末に終了する一般NISAが新NISAに生まれ変わります。
これに合わせて、「つみたてNISA」や「ジュニアNISA」も少し制度変更があります。
最初に変更点のポイントを5つにまとめました。
- つみたてNISAは5年延長
- 一般NISAは2024年から2階建ての新NISAに移行
- 投資経験者は2階のみ使うこともできるが、おすすめしない
- 一般NISAから新NISAへの移行は複雑
- ジュニアNISAは制度終了
NISAは3種類
変更点を理解するために、現状のNISAについて簡単に触れておきます。
NISAには、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3つの種類があります。
一般NISAとは?
最大運用期間5年を目安に、上場株式や当信託の譲渡益や配当金・分配金が非課税になる制度です。
年間120万円の上限金額のある一般NISAですが、非課税となる譲渡益や配当については上限はありません。
譲渡益がどれだけ増えても約20%の税金がかからないことがポイントです。
つみたてNISAとは?
つみたて投資に特化した小額非課税制度です。
金融庁により厳選された金融商品の中から、年間上限金額を40万円に対して得られた利益が最長20年間非課税になります。
ジュニアNISAとは?
未成年者向け小額非課税制度です。
年間80万円を上限に、5年間非課税で運用できる制度です。
一般NISAと異なり、子供が18歳まで引き出しができないなど、デメリットもあります。
税制改正後のNISAの変更点について
つみたてNISAの変更点には?
まずは、変更点がわかりやすい「つみたてNISA」から見ていきます。
つみたてNISAの変更点は、投資開始期間が5年延長されたのみです。
詳しく解説すると、これまで新規に投資できる期間が2037年まででしたが、税制改正により2042年までとなり5年延長されました。
仮に2020年からつみたてNISAを利用を始めたとすると、つみたて期間は「40万円×23年=920万円」となります。
しかし、非課税期間の最長20年は制度改正後も変更されていないため、「40万円×20年=800万円」が非課税枠となります。
これまで通り20年以上ロールオーバーができないところにご注意ください。
ジュニアNISAの変更点は?
ジュニアNISAは、当初の予定通り2023年末で終了します。
税制改正後の変更点は、制度終了後の2024年移行はいつでも引き出しが可能(一括引き出しのみ)になります。
また、引き出しをしない場合も翌年にロールオーバーすることにより、子供が18歳になるまで継続保有すること(継続管理勘定)が可能になりました。
新NISAの変更点は?
一般NISAは、2023年末で新規投資枠の終了に伴い、2024年から新NISAとして生まれ変わります。
そして、投資できる期間も2024年から2028年の5年間延長となります。
新NISAへの移行について複雑なので、3つのパートを分けてお伝えします。
- 新NISAの活用方法
- 投資経験者は2階部分のみ利用可能(非推奨)
- 一般NISAから新NISAにロールオーバーする場合
新NISAの活用方法
新NISAの一番の特徴は、2階建てとなる投資方法にあります。
新NISAでは原則1階部分(つみたてNISA対象商品の積立)を利用しないと、2階部分を利用することができません。
また、利用できる枠も一般NISAの120万円から、新NISAでは1階部分が20万円(全額埋める必要なし)、2階部分が102万円までと上限金額も変更されています。
ちなみに、2階部分の投資対象商品は、レバレッジを効かせている投資信託や上場株式のうち整理銘柄・管理銘柄を除いた上場株式・投資信託・ETF・REITに投資することが可能です。
102万円は一括購入も、積立投資のどちらで購入しても問題ありません。
つみたてた1階部分はどうなる?
5年間つみたてた1階部分については、制度終了後に「つみたてNISA」にロールオーバーすることが可能です。
つみたてNISAに移行後は、つみたてNISAの上限額40万円まで新規投資することもできます。
投資経験者は2階部分だけを利用可能(非推奨)
これまでNISA口座を利用している人や上場株式などを運用したことのある投資経験者は、証券会社などに届出を提出すれば、例外として2階部分のみを利用することができます。
ただし、2階部分のみを利用する場合に投資できる対象商品は、個別株のみになります。
投資信託やETF、REITなどを買うことができません。
これらを利用したい場合は、1階部分を利用する必要があります。
また、年間の投資枠も2階部分のみ102万円までとなり、現行の制度より上限金額も減額されるため、2階部分のみを利用することはあまりおすすめしません。
一般NISAから新NISAへのロールオーバーする場合
これまで一般NISAを利用していた人は、新NISAの投資枠(1階2階を合わせた122万円)を超えていても全額ロールオーバーすることが可能です。
例えば、2019年に一般NISA枠で購入した商品が140万円になっていたとしても全額ロールオーバーすることが可能です。
ただし、新NISAで対象外となるレバッジを効かせた投資信託や上場株式のうち整理銘柄や管理銘柄のロールオーバーはできないので、注意が必要です。
また、一般NISA枠で購入した商品が新NISAの122万円以内に収まる場合は、2階部分から埋めていくことになります。
例えば、2019年に購入した商品が110万円になった場合、2階部分の102万円の枠を最初に埋めて、残りを1階部分で利用することになります。
しかし、1階部分は8万円しか利用していないため、残り12万円分を利用することが可能となります。
ただし、1階での利用となるため対象商品はつみたてNISA対象品のみの積立限定となります。
さらに一般NISA枠で購入した商品が2階部分の102万円以内に収まる場合はどうなるのか?
例えば、2019年に購入した商品が80万円だった場合、まずは2階部分の枠を80万円分を使います。
2階部分に22万円分の余りが発生しますが、22万円の残りをすぐ使えるわけではなく、まず1階部分を先に埋める必要があります。
1階部分を使い切ったのち、22万円の残り枠を使用することができます。
まとめ:新NISA制度は少し複雑
税制改正によって2024年から生まれ変わる新NISAについてお伝えをしました。
新NISAは2階建て制度に変更されるため、これまで一般NISAを使っていたほユーザーにとっては、使いづらく複雑な制度になります。
一方、つみたてNISAをしているユーザーにとってはそれほど変わらない制度変更になります。
これからNISAを始める人には、つみたてNISAから始めた方がお得と言えるかもしれません。
ただし細い部分の制度は、2024年までにいくつか追加・変更されると思うので、必ずしもつみたてNISAの選択が最適というわけでもありません。
各自の生活スタイルや必要なお金を考えた上で、利用できる制度を上手に利用することが大切です。