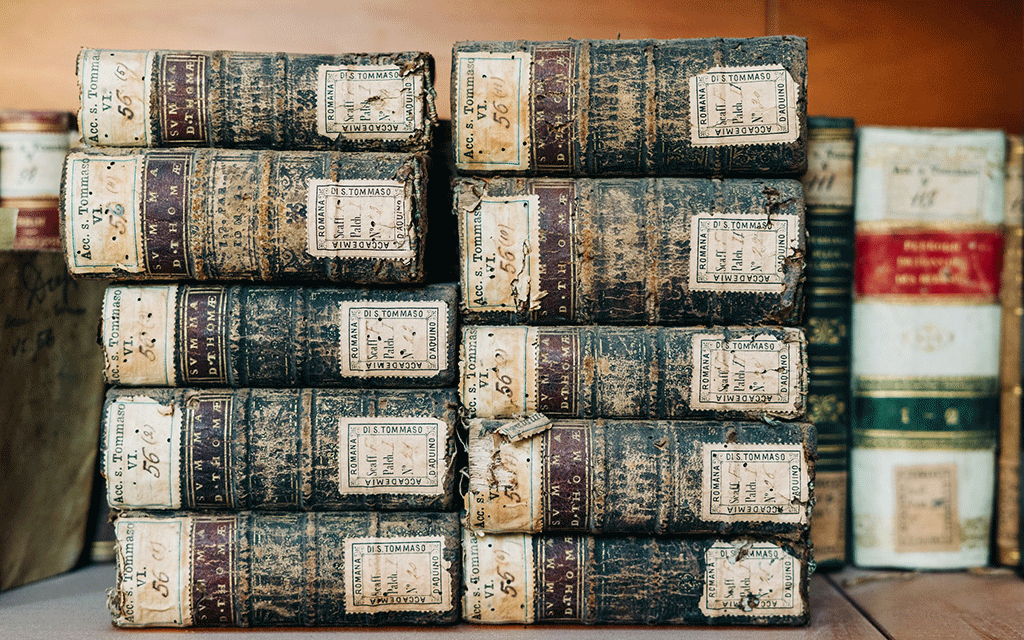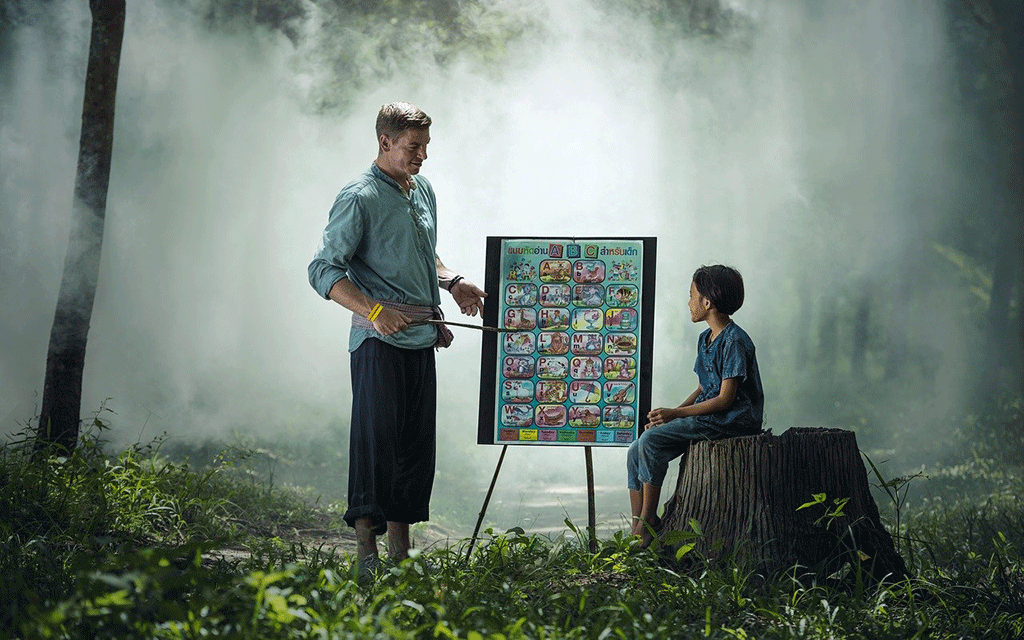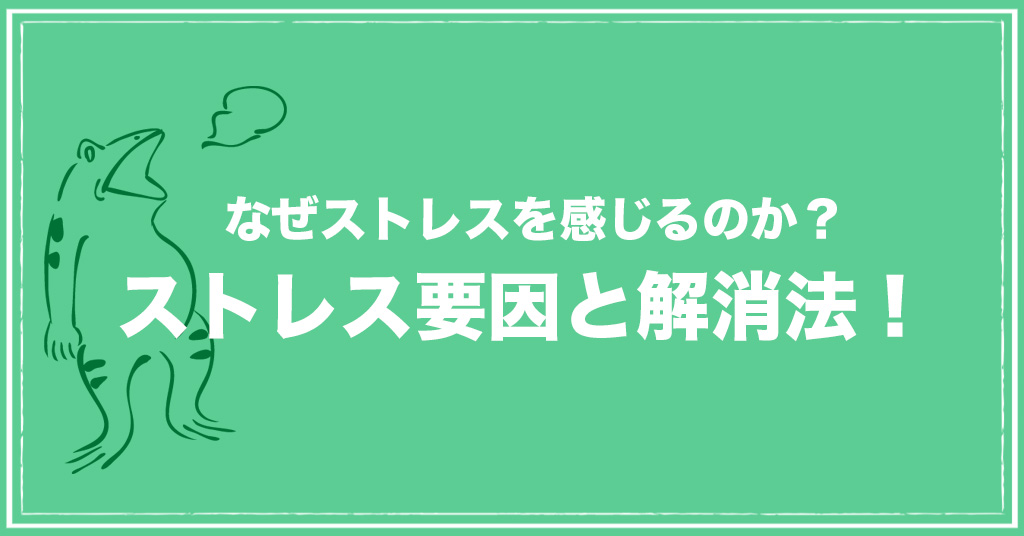
仕事や人間関係、老後の資金など、不安やストレスを感じる要素は人それぞれ。
ストレスとは、外部からの刺激によって精神・身体・環境のバランスに圧力がかかり、心や身体に負担のかかった状態のことをいいます。
この状態が長く続くと、不安やイライラ、肩こり、偏頭痛など精神から身体へ悪影響があらわれ、引きこもりやアルコール依存症、うつ病といった心の病に発展してしまいます。
 アシのMちゃん
アシのMちゃん 心や身体の負担を軽くするにはどうすればいいですか?
ストレスの要因は、一つに絞ることができません。
外部からくる刺激(要因)による反応が、色々な形で心や身体に不調のサインとしてあらわれるからです。
 Yoshinori
Yoshinori ストレスは、要因と反応からくる2つのストレス要因を解決する必要があります。
昔から同じような悩みを抱え、いつまで経ってもストレスが解消しないのは、ストレスの要因とそれによる反応からくる2つのストレスを解決していないためです。
この記事では、ネットや書籍、取材を通して集めたストレスに関する知識やストレスが及ぼす悪影響、その解決法をご紹介します。
ストレスとは?

ストレスは、カナダの生理学者ハンス・セリエ氏が唱えた「ストレス学説」を根源としています。
ストレスとは、外部環境からの刺激によって刺激の性質と異なる固体防衛反応が心や身体に不調のサインとして出ることをさします。
(例)上司に怒られて不眠症になってしまった場合のストレス反応
1.ストレス要因(外部刺激)
上司に叱責されて、怒りや悲しみを覚える
2.ストレス反応
イライラや不安から不眠症になり眠れなくなる
このように、ストレスには外部刺激によるきっかけと刺激の性質とは異なる防衛反応が不調のサインとして心や身体にあらわれます。
ストレス学説では、外部刺激によるきっかけのことを「ストレッサー」と呼び、それによる防衛反応を「ストレス」と呼んでいます。
つまり、ストレスを解決するためには、ストレスの要因であるストレッサーとそれによる防衛反応の2つを解決する必要があるということです。
上記の例では、以下のストレス対策が有効です。
叱責されて落ち込むことへの対策(ストレス要因)
イライラや不安からくる不眠症対策(防衛反応)
これら2つの悩みを解決することがストレス対策となります。
ストレスの要因と種類

ストレスを引き起こす要因(ストレッサー)は、その人の悩みからきています。
人の悩みは、大きく4つに分類できます。
- 健康(Health)
- 将来への不安(Ambition)
- 人間関係(Relation)
- お金(Money)
それぞれの頭文字を取り、「HARMの法則」と呼ばれる人の悩みの根源です。
そして、ストレッサーによって引き起こされるストレスには、3つの特徴があるとブログ「パレオな男」で人気のライター 鈴木 祐さんの書かれた「超ストレス解消法」で紹介されています。
- ショート:目の前の短期的なストレス
- ループ:繰り返しループするストレス
- ロング:ループするストレスが慢性化して、麻痺してしまう状態
本書では、この中で解決しなければいけないストレスを「ロングのストレス」と定めています。
長期にわたるストレスは、心の不調としてあらわれ、日常生活に支障をきたすからです。
ストレス反応とその症状

一般的にストレスを抱えながら頑張り続けると、「身体→人間関係→行動→心」の順番に異変が起こるとされています。
ストレスを抱えると、まずはじめに不眠症や胃のムカつき、倦怠感といった身体に不調のサインとしてあらわれます。
次に身体の不調からくるイライラや怒りから、周囲の人に厳しくなり、人間関係に異変が起こり始めます。
人間関係に異変が起こると思考が短絡的になり、人と関わることを避けるようになったり、暴力的な行為に訴えたりなど行動が少しずつ変容していきます。
「最近、あの人変わったね」などと囁かれたりするのは、人間関係のもつれからくる思考力の欠如が原因です。
この状態で無理をし続けると、仕事でミスを連発したり、他人の意見をまともに聞けなくなり、うつ病や精神疾患を発症してしまいます。
最近、「仕事で単純ミスが多い」「一つのことに集中できなくなった」などの経験のある人は、一度立ち止まって無理をしすぎていないか考えてください。
ただし、ストレスを抱えやすい人は、無理をしていることを自覚できません。
周囲の人の声に耳を傾けたり、無駄でもいいので無理やり休むようにしましょう。
心当たりがあり心配をされる方は、専門機関に相談しましょう。
ストレスアプリのアフィリエイトを掲載
ストレスを抱えやすい人の特徴
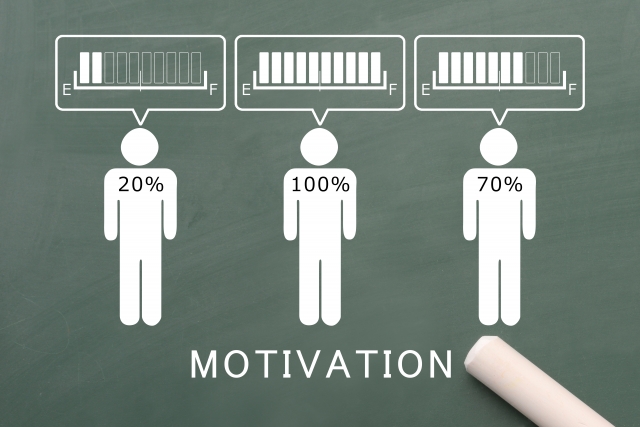
ストレスを抱えやすい人は、目の前の目標に意識を集中する傾向にあります。
目の前の目標とは、
- 今週末のテストで良い点を取る
- 今週中に売り上げ目標を達成する
- 明日までに溜まっている仕事を片付ける
など、差し迫った目標に向かって頑張ることです。
目標に向かって頑張っているため、周囲からは「充実した毎日を過ごしている人」に見えますが、短期的な目標を持って頑張ると燃え尽き症候群になりやすいという報告があります。
短期的な目標は3ヶ月に2・3回程度であれば、人生をよくするためのガソリンとして有効に機能します
ただし、短期間で何度もガソリンを入れ続けて走り続けると燃え尽き症候群になってしまいます。
(例)1キロの距離を走る場合
- ペース配分を意識しながら走る
- 100mを10本全力疾走する
上記の場合では、ペース配分を意識しながら走る方が、100mを10本全力疾走で走るより、快適かつ楽に1キロの距離を走ることができます。
また、その後に距離が追加されたとしても引き続き走ることができます。
短期的な目標ばかりを掲げると、常に全力疾走している状態になります。
そのため、人生という長い距離を走り切ることができなくなります。
短期の目標を追ったり、周囲のペースに惑わされたりせず、自分が楽に走れるペースを見つけて頑張るようにしましょう。
そして、時には休むことも重要です。
ストレスの限界サイン

ストレスは「身体→人間関係→行動→心」の順番で異変が生じると解説をしました。
ストレスによる限界サインは、まず身体の不調としてあらわれます。
身体の不調には、以下のようなものがあります。
- 食欲の不調
- 睡眠の不調
- 性欲の不調
うつ病の患者は、食事に喜びを見いだせないという症状があります。
また、ストレスの多い出来事を経験すると不眠症のリスクが増加するという研究結果もあります。
食べることに興味がなくなったり、朝起きるのが辛い、毎晩睡眠の途中で目が覚めてしまうなど、以前のように生活できなくなった人は要注意です。
また、ストレスは性欲にも影響を与えます。
アメリカのベイラー医科大学で339名の男女に対して行ったアンケートでは、ストレスレベルが高いと性欲や満足度に悪影響が出るという結果が発表されました。
ストレスによる症状には個人差があります。
精神面や肉体面でこれまでと異なる悩みに気づいたときは、その変化に注目して無理をせず休むようにしましょう。
2つの不調に対するストレス対策
ストレスは、ストレスの要因となるストレッサーと防衛反応による不調の2つに対して対策が必要です。
ストレッサーへの対策は、思考と栄養、そして受容のバランスを取ることです。
ストレッサーを引き起こす要因は、人の悩み(HARMの法則)です。
人の悩みは、健康・将来への不安・人間関係・お金に対する考え方や栄養の偏り、決めつけ思考による自責や他責がストレスの要因となっています。
栄養の偏りによる健康被害は言うに及ばず、将来への不安や人間関係、お金などへの不満は、考え方とそれを受け入れる気持ちの問題です。
しかし、多くの人はストレッサーによるストレスを受け入れることができません。
人は主観的な生き物で、自分のことを客観視できないからです。
将来への不安や人間関係、お金への不満は、すべて主観による被害妄想です。
将来成功するかどうかはわからないし、他人から嫌われていると思うのは、勝手な決めつけによるただの勘違いです。
また、お金への不満は他人と自分の状況を比べることによる意味のない自責です。
人は、他人の言葉より頭の中に流れる自分の言葉を一番多く聞いています。
頭の中に流れる主観的なネガティブ発言を聞き続けた結果、被害妄想に囚われストレスに苛まれています。
主観による決めつけから逃れる方法
主観による決めつけから逃れるには、主観による決めつけを分析し、それを取り払うことです。
決めつけを分析するには、以下の5つのステップを用います。
- ストレスの状況を確認する
- ストレス感情に点数をつける
- 点数をつけた理由と背景を考える
- ストレスに対する感想と事実(根拠)を確認する
- 感想と事実に反論する
決めつけによる主観を分析することによって、感情と事実を切り離して物事を客観視できるようになります。
そうすることで、思い込みによるストレスを解消することができるようになります。
ただし、思い込みによるストレス以外のことは、ただ受け入れるしかありません。
抗っても意味はないので、現状を受け入れて、必要以上にそのストレスに目を向けず、日常をただ繰り返してください。
日常生活をただ送ることで、少しずつストレスから解放されて普段の日常に戻ることができるようになります。
防衛反応に対するストレス発散法
ストレッサーから来る防衛反応による不調は、生活習慣を整えることで健康な状態に戻すことができます。
生活習慣を整えるために必要なのは、運動と食事です。
運動は、集中力や記憶力アップ、メンタルの強化に効果があります。
毎日10分から30分程度のウォーキングだけでも大丈夫です。
時間のあるときに、近所の公園を少し早足で散歩するようにしましょう。
食事のポイントは、お酒と糖分を控えることです。
お酒や糖分を過剰に摂取すると、体内炎症濃度が上がり、健康被害につながる要因となります。
体内の炎症濃度を上げないためには、栄養素の豊富な食品を摂取することが重要です。
栄養素の豊富な食品とは、ビタミン・ミネラル・必須アミノ酸、オメガ3脂肪酸が多く含まれている食品です。
▼栄養素の豊富な食品例
- 全粒穀物
- 野菜
- フルーツ
- 魚介類
- 鶏肉
- 赤身肉
- 豆・ナッツ類
- オリーブオイル
- チーズ
- 生活習慣を整える運動と健康的な食生活を送ることで、ストレス耐性を上げることができます。
- 気分が落ち込んだ時などは、生活習慣を見直すことから始めましょう。
ストレスのメリット
ここまでストレスによる健康被害やその対処法について解説をしました。
しかし、ストレスはデメリットばかりではありません。
適度なストレスは、人生を豊かに、また不安から抜け出す糧にもなります。
乗り越えられないストレスは健康被害をもたらしますが、乗り越えられるストレスは成長する力を与えてくれるからです。
ストレスを自分を成長させる糧とするには、自らそのストレスに飛び込むことです。
人は外部からくる刺激には弱い生き物ですが、自ら向かっていく刺激には力強く抵抗することができます。
自らストレス状況に飛び込むことにより、心構えや事前対策をとることができるからです。
ストレスは、捉え方次第で毒にも薬にもなります。
ストレスを避けることばかりを考えるのではなく、時には自らストレスのかかる状況に身を置いて成長する糧としましょう。
そうすることで、強いメンタルを手に入れることができ、ストレス耐性を身につけることもできるようになります。
まとめ
ストレスの要因と対策、発散法について解説をしました。
ストレスは誰もが抱える現代病です。
ストレスの要因は、主観によるきめつけや無理をしすぎることによる心と体の不調です。
ストレスは、身体→人間関係→行動→心の順番に異変を生じさせます。
まずは、身体の不調のサインを見逃さず、「最近無理をしているな」と感じたら、すぐに休むよう心がけてください。
最も有効的なストレス対策は、自分にやさしくすることです。
自分にやさしくすることで、ストレス耐性を上げ、またストレスによる不調から逃れることができるようになります。
最近、身体に不調を感じる人は自分自身に優しい言葉をかけて、心と体を休めるようにしてください。